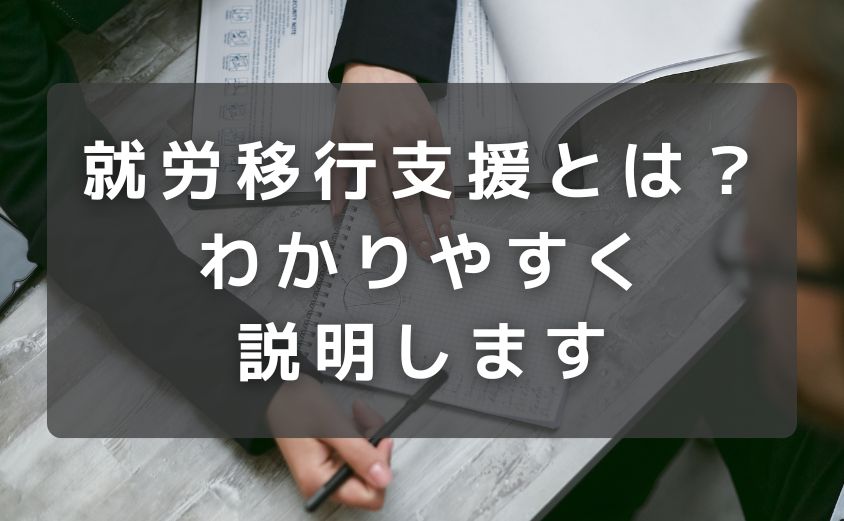「就労移行支援って何?」がスッキリわかる!あなたの未来を広げる第一歩
「就労移行支援ってよく聞くけど、具体的にどんなことをしてくれるの?」
「自分も利用できるのかな?」「どこに相談したらいいんだろう…」
そんな疑問を抱えて、このページにたどり着いたのではないでしょうか?
障害や体調の問題で「働きたいけど不安がある」「何から始めればいいかわからない」と感じている方にとって、就労移行支援は大きな助けになる制度です。でも、初めて知った人にとっては「専門用語が多くて難しそう…」と感じてしまうこともありますよね。
大丈夫です。この記事では、 「就労移行支援とは何か?」を、できるだけシンプルでわかりやすく解説 します。さらに、「どんなサポートが受けられるのか」「どんな人が利用できるのか」「実際に就職できるのか?」といった気になるポイントも、実際の成功事例を交えながら紹介します。
この情報を知れば、不安が希望に変わる!
たとえば、過去に「働きたいけど、自分に合った仕事がわからない」と悩んでいたAさん。就労移行支援を利用し、職業訓練や実習を経て、自分にぴったりの職場に出会うことができました。今では自信をもって働き、安定した生活を手に入れています。
就労移行支援をうまく活用することで、あなたも「自分にできる仕事が見つかった!」「無理なく働ける環境に出会えた!」と感じる未来が待っています。
この記事を読むと、こんなメリットがあります!
✅ 就労移行支援の仕組みが簡単に理解できる
✅ あなたが利用できるかどうかがわかる
✅ 支援を活用することで、どんな未来が待っているのかがイメージできる
✅ 就職への第一歩を踏み出す勇気がもてる
「就職したいけど不安…」というあなたにこそ、知ってほしい情報を詰め込みました。この記事が、あなたの一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
1. 就労移行支援とは?
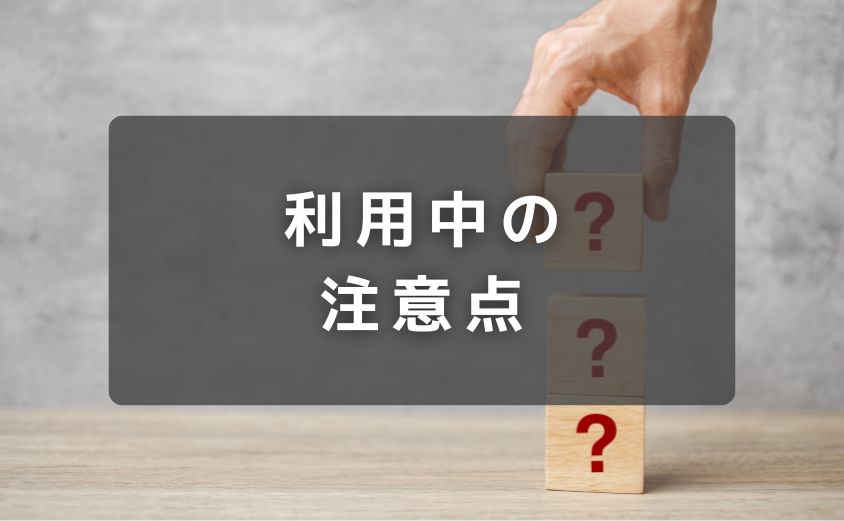
就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すためのサポートを受けられる福祉サービスです。
個々の障害特性や状況に応じたトレーニングや支援が提供され、就職から定着までをサポートします。

就労移行支援は、障害のある方が働くための準備をする場所です。
職業訓練や就職活動の支援を受けられます。
- 就労移行支援の基本情報
- 就労移行支援を利用できる人
就労移行支援は、働くことに不安を感じる方や、職場での適応が難しい方にとって重要な支援制度です。
次に、就労移行支援の基本情報について詳しく解説します。
1.1. 就労移行支援の基本情報
就労移行支援は、障害のある方が自立して働けるように、さまざまなサポートを提供する福祉サービスです。
障害者総合支援法に基づき、一定の条件を満たす方が利用できます。
- 就労移行支援の目的:一般企業への就職を支援
- 対象者:身体・知的・精神障害、発達障害、難病など
- 支援期間:原則2年間(延長制度あり)
たとえば、うつ病で長期間働けなかった方が、就労移行支援を利用し、少しずつ働く準備を整え、最終的に企業へ就職するケースがあります。
また、発達障害の方が職場でのコミュニケーションが苦手な場合、トレーニングを通じてスムーズに働けるスキルを身につけることも可能です。
このように、就労移行支援は個々の状況に合わせた支援を提供し、スムーズな就職につなげる役割を担っています。
次に、就労移行支援を利用できる人について詳しく解説します。
1.2. 就労移行支援を利用できる人
就労移行支援を利用できるのは、障害者総合支援法に基づき、特定の障害や疾患を持つ方です。
具体的には、以下のような方が対象となります。
- 身体障害者(視覚・聴覚・肢体不自由など)
- 知的障害者(軽度から中度の知的障害を含む)
- 精神障害者(うつ病・統合失調症・双極性障害など)
- 発達障害者(ASD・ADHD・LDなど)
- 難病患者(指定難病を持ち、就労が困難な方)
例えば、統合失調症の方が就労移行支援を利用し、少しずつ職場復帰を目指すケースがあります。
また、ASD(自閉症スペクトラム障害)の方が、職場での適応トレーニングを受けながら、自分に合った働き方を模索することも可能です。
このように、さまざまな障害や疾患を持つ方が利用できる就労移行支援ですが、利用を開始するためには手続きが必要です。



就労移行支援は、身体・知的・精神・発達障害の方や難病の方が対象です。
事前に条件を確認しましょう。
次に、就労移行支援で受けられる具体的なサービス内容について解説します。
2. 就労移行支援で受けられる具体的なサービス内容
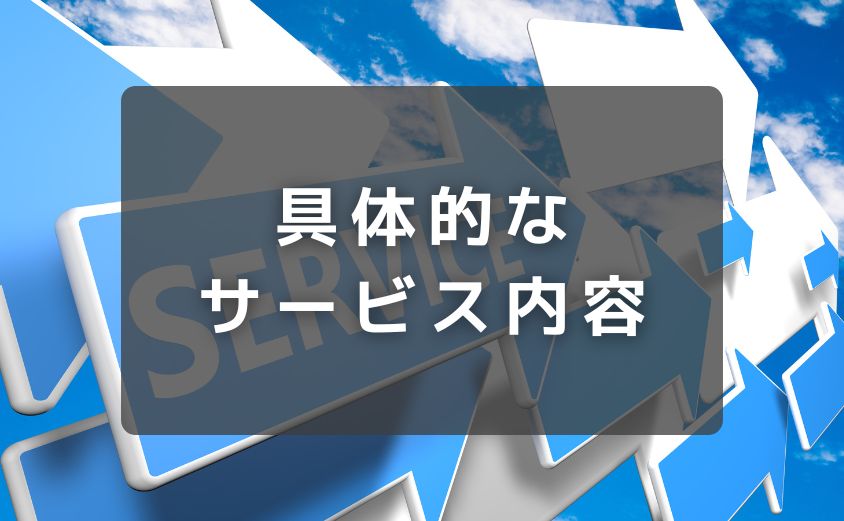
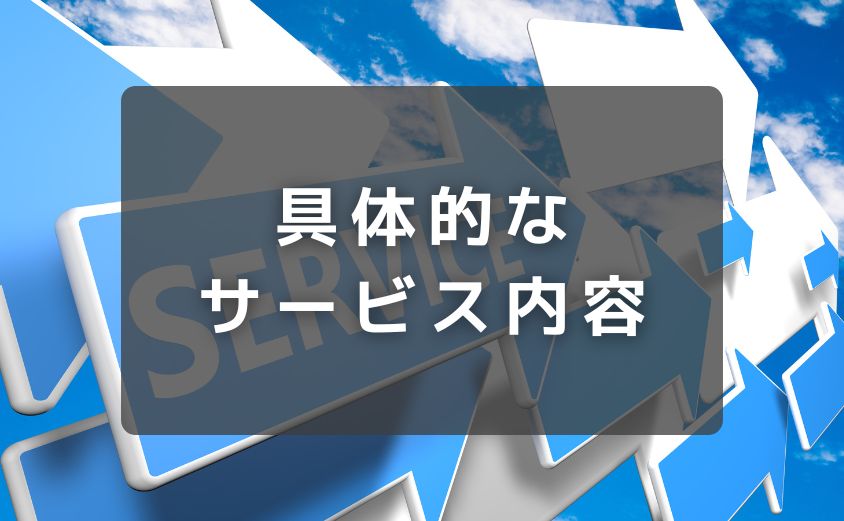
就労移行支援では、就職を目指す方に向けたさまざまなサポートが提供されます。
職業訓練や就職活動の支援、就職後の定着支援まで幅広いサービスが含まれます。



就労移行支援では、仕事に必要なスキルの習得や、就職活動のサポートを受けられます。
さらに、就職後も定着できるようにフォローが続きます。
- 就職に向けたトレーニング内容
- 就職活動のサポート
- 就職後の定着支援(アフターフォロー)
これらの支援を受けることで、就職の可能性を広げ、長く働ける環境を整えることができます。
次に、就職に向けたトレーニング内容について詳しく見ていきましょう。
2.1. 就職に向けたトレーニング内容
就労移行支援では、就職に向けた実践的なトレーニングを受けることができます。
働くために必要なスキルや知識を身につけ、職場に適応できるように準備します。
- ビジネスマナーの習得(挨拶、敬語、報連相など)
- コミュニケーション能力の向上(会話練習、対人関係スキル)
- パソコン(PC)スキルの習得(Word、Excel、メールの使い方)
- 作業訓練・職業体験(軽作業、データ入力、接客など)
- 自己理解やメンタルケア(ストレス対処、自己分析)
例えば、ビジネスマナーのトレーニングでは、正しい敬語の使い方や名刺交換の方法を学びます。
また、パソコンスキルの訓練では、実際にWordやExcelを使い、業務で役立つスキルを身につけます。
このようなトレーニングを受けることで、安心して職場に適応できる準備を整えられます。



就職に必要なスキルを学べるので、働く自信がつきます。
特に、ビジネスマナーやPCスキルはどの仕事でも役立ちます。
次に、就職活動のサポートについて詳しく解説します。
2.2. 就職活動のサポート
就労移行支援では、就職活動をスムーズに進めるためのサポートも充実しています。
履歴書の作成や面接対策、企業とのマッチングなど、就職に向けた具体的な準備を進められます。
- 履歴書・職務経歴書作成の支援(書き方の指導、添削)
- 面接練習・模擬面接(質問対策、身だしなみ指導)
- 就労先の開拓・紹介(希望に合った職場の提案)
- 企業見学・実習のサポート(職場体験の手配)
- ハローワーク同行・手続き支援(求人検索、応募手続きの補助)
例えば、面接が苦手な方は、模擬面接を何度も行い、実際の面接で自信を持って話せるようになります。
また、企業見学や実習に参加することで、職場の雰囲気を知り、自分に合う環境かどうかを確認できます。
このような支援を活用することで、より安心して就職活動を進めることができます。



履歴書の書き方や面接対策をしっかり準備できます。
企業見学や実習を活用すれば、就職のミスマッチを防げます。
次に、就職後の定着支援について詳しく解説します。
2.3. 就職後の定着支援(アフターフォロー)
就労移行支援では、就職後の定着をサポートするアフターフォローも提供されます。
仕事に慣れるまでの期間や、働き続けるための課題に対して、継続的な支援を受けることができます。
- 職場での悩み相談(人間関係や業務の不安を解消)
- 企業と連携したサポート(職場との調整・トラブル対応)
- 定期的な面談やフォローアップ(働き続けるためのアドバイス)
例えば、新しい環境に慣れるまでの間、定期的な面談を通じて仕事の悩みを相談できます。
また、企業側と連携し、無理なく働き続けられるよう調整を行うことも可能です。
このように、就職後も安心して働けるように、しっかりとしたサポート体制が整っています。



仕事を長く続けるためのサポートが受けられます。
職場の悩みを相談できる環境があるので安心です。
次に、就労移行支援の利用料金と利用期間について詳しく解説します。
3. 就労移行支援の利用料金と利用期間
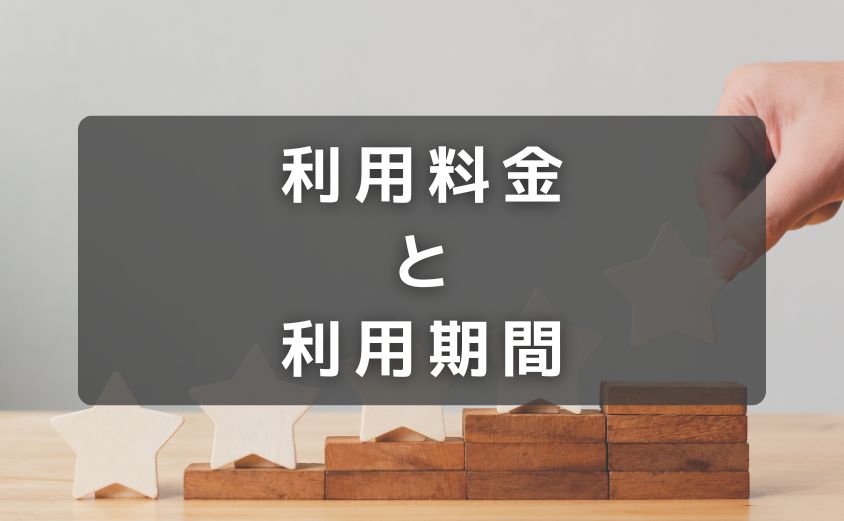
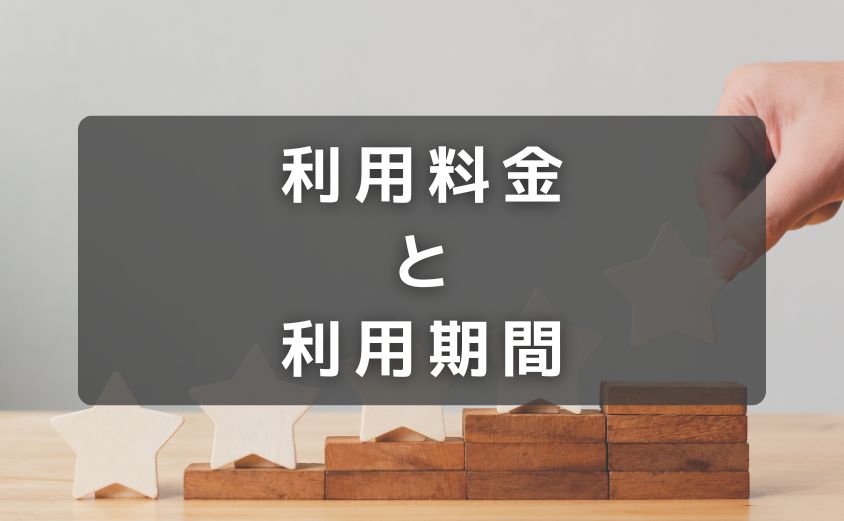
就労移行支援は基本的に無料で利用できますが、世帯収入によっては自己負担が発生することがあります。
また、利用期間は原則2年間と決められており、一定の条件を満たせば延長も可能です。



就労移行支援の利用料金は原則無料です。
ただし、世帯収入によって自己負担が発生することがあります。
私は、世帯収入の関係で支払いが発生しました。
- 利用料金・費用について
- 利用期間と終了の条件
費用面が気になる方は、事前に確認しておくと安心です。
次に、利用料金や費用について詳しく解説します。
3.1. 利用料金・費用について
就労移行支援の利用料金は、障害福祉サービスの制度に基づき、原則無料です。
ただし、世帯の収入状況によっては自己負担が発生する場合があります。
- 生活保護受給世帯:自己負担なし
- 低所得世帯(住民税非課税):自己負担なし
- 一般世帯(住民税課税):月額9,300円が上限
- 一定以上の所得世帯:月額37,200円が上限
例えば、生活保護を受けている方や住民税が非課税の方は、費用の自己負担はありません。
一方で、一定以上の収入がある世帯は、最大37,200円の自己負担が発生する可能性があります。
このように、収入状況によって自己負担額が異なるため、事前に自治体や事業所に確認することが重要です。



多くの方が無料で利用できますが、収入によっては費用がかかる場合があります。
事前に自治体に相談すると安心です。
次に、就労移行支援の利用期間と終了の条件について解説します。
3.2. 利用期間と終了の条件
就労移行支援の利用期間は、原則2年間と定められています。
ただし、状況によっては延長できる場合もあります。
- 原則2年間の利用(1年ごとに更新審査あり)
- 延長可能な条件(特別な事情がある場合に限る)
- 終了の条件(就職が決まる、または利用期間満了)
例えば、体調が安定せずすぐに就職が難しい場合、延長が認められることがあります。
また、途中で就職が決まった場合は、利用期間内であってもサービスが終了します。
このように、利用期間には一定のルールがあるため、自分の状況に合わせて計画的に利用することが大切です。



原則2年間ですが、特別な事情があれば延長できる可能性もあります。
計画的に利用することが重要です。
次に、就労移行支援のメリット・デメリットについて解説します。
4. 就労移行支援のメリット・デメリット


就労移行支援を利用することで、多くのサポートを受けられますが、メリットだけでなくデメリットもあります。
利用を検討する際は、それぞれの特徴を理解して、自分に合っているかを確認することが大切です。



就労移行支援には、多くのメリットがありますが、人によってはデメリットを感じることもあります。
自分に合った支援を選びましょう。
- 利用するメリット
- 利用するデメリット・注意点
それぞれのポイントを詳しく解説します。
4.1. 利用するメリット
就労移行支援を利用することで、就職活動や職場で働くための準備を整えることができます。
特に、仕事探しや職場での適応が不安な方にとって、大きな助けとなります。
- 自分に合った仕事を見つけやすい(適性診断や職業体験が可能)
- 生活リズムを整え、体調管理ができる(規則正しい通所で習慣化)
- 就職までの支援が充実している(面接対策や企業見学が可能)
- 同じ境遇の人と交流できる(仲間と励まし合いながら訓練できる)
例えば、職業訓練を受けながら自分の得意なことや苦手なことを整理し、適職を見つけることができます。
また、生活リズムを整えながら通所することで、就職後の安定した生活習慣を作ることができます。
このように、就労移行支援は就職準備を整える上で大きなメリットがあります。



就職に向けたサポートが充実しているので、自分に合った仕事を見つけやすくなります。
生活リズムを整えられる点も魅力です。
次に、利用する際のデメリットや注意点について解説します。
4.2. 利用するデメリット・注意点
就労移行支援には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。
事前にデメリットを理解し、対策を考えておくことが重要です。
- すぐに就職できるとは限らない(準備期間が必要)
- 専門的なスキルの習得が難しいことがある(基礎訓練が中心)
- 訓練内容が合わないとモチベーション低下につながる(事前の確認が必要)
例えば、短期間で就職したい方には、訓練期間が長く感じることがあります。
また、プログラミングやデザインなどの専門的なスキルを学びたい場合、就労移行支援の内容では不十分に感じることもあります。
自分の目的に合った事業所を選ぶことが、就労移行支援を有効に活用するポイントです。
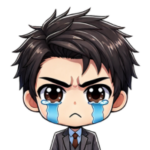
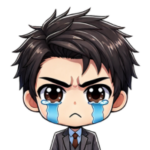
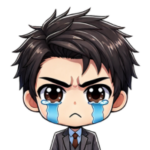
就労移行支援は万能ではありません。
事前に訓練内容や就職サポートの内容を確認しておきましょう。
次に、就労移行支援と就労継続支援の違いについて解説します。
5. 就労移行支援と就労継続支援の違い
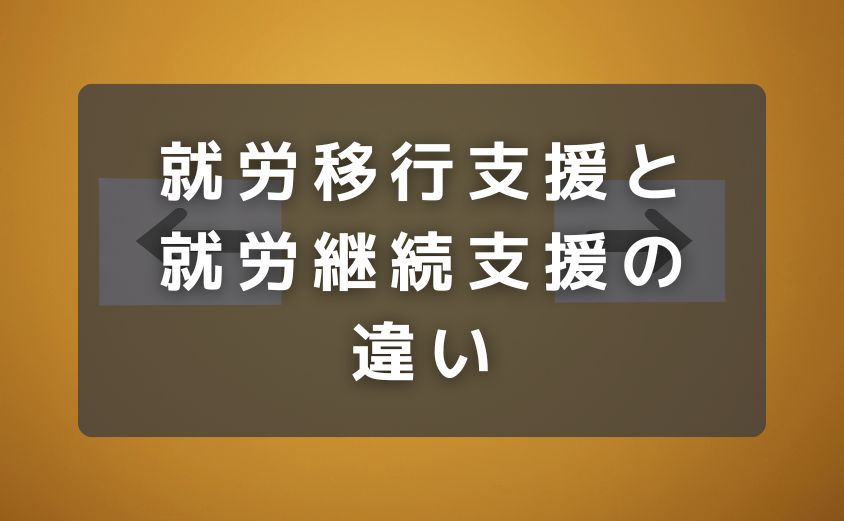
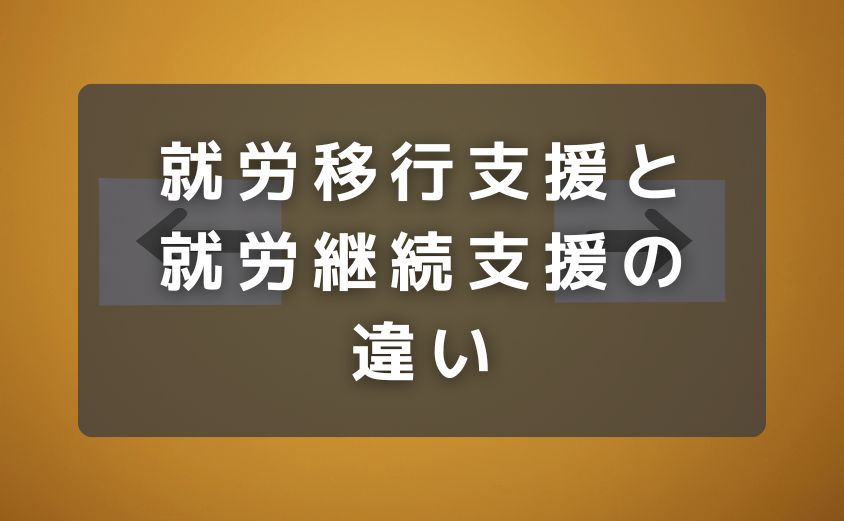
就労移行支援と就労継続支援は、どちらも障害のある方の就労をサポートする福祉サービスですが、目的や支援内容が異なります。
自分に合った支援を選ぶために、それぞれの特徴を理解することが大切です。



就労移行支援は「一般就労を目指す人向け」、就労継続支援は「福祉的な働き方を希望する人向け」です。
- 就労移行支援とは
- 就労継続支援とは
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
5.1. 就労移行支援とは
就労移行支援とは、一般企業への就職を目指す障害のある方をサポートする福祉サービスです。
職業訓練や就職活動のサポートを通じて、自立した働き方を実現するための支援を受けられます。
- 目的:一般企業への就職を目指す
- 対象者:身体・知的・精神・発達障害、難病の方
- 支援内容:職業訓練、就職活動サポート、定着支援
- 利用期間:原則2年間
例えば、うつ病で長期間働けなかった方が、就労移行支援で訓練を受け、少しずつ職場復帰を目指すケースがあります。
また、発達障害の方が職場での対人関係に不安を感じる場合、コミュニケーションスキルのトレーニングを受けることで、働く自信をつけることができます。
このように、就労移行支援は一般企業での就職を目指す方にとって、重要なサポートを提供します。



一般企業への就職を目指すなら、就労移行支援を活用しましょう。
職業訓練や就職活動のサポートが受けられます。
次に、就労継続支援について詳しく解説します。
5.2. 就労継続支援とは
就労継続支援とは、一般企業での就職が難しい障害のある方が、福祉的な支援のもとで働くことができる制度です。
A型(雇用型)とB型(非雇用型)の2種類があり、それぞれ働き方や支援内容が異なります。
- 目的:一般企業での就職が難しい方の就労支援
- 対象者:身体・知的・精神・発達障害、難病の方
- 種類:A型(雇用契約あり)、B型(雇用契約なし)
- 支援内容:軽作業や事務作業などの業務提供
例えば、就労継続支援A型では、事業所と雇用契約を結び、最低賃金が保証された仕事をすることができます。
一方、B型は雇用契約がないため、体調に合わせて自由なペースで働ける点が特徴です。
このように、一般企業での就労が難しい場合でも、就労継続支援を利用すれば働く機会を得ることが可能です。



就労継続支援は、無理なく働ける環境が整っています。
A型は雇用契約あり、B型は自由なペースで働けます。
次に、就労移行支援事業所を選ぶ際のポイントについて解説します。
6. 就労移行支援事業所を選ぶ際のポイント
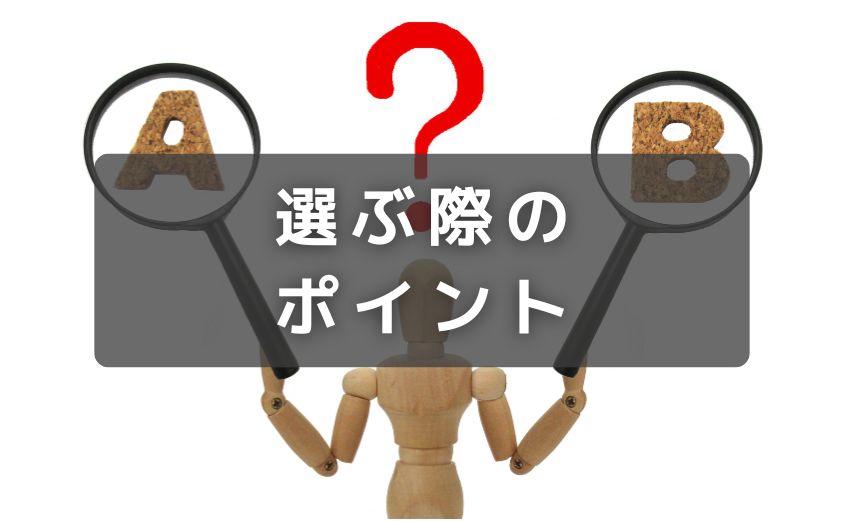
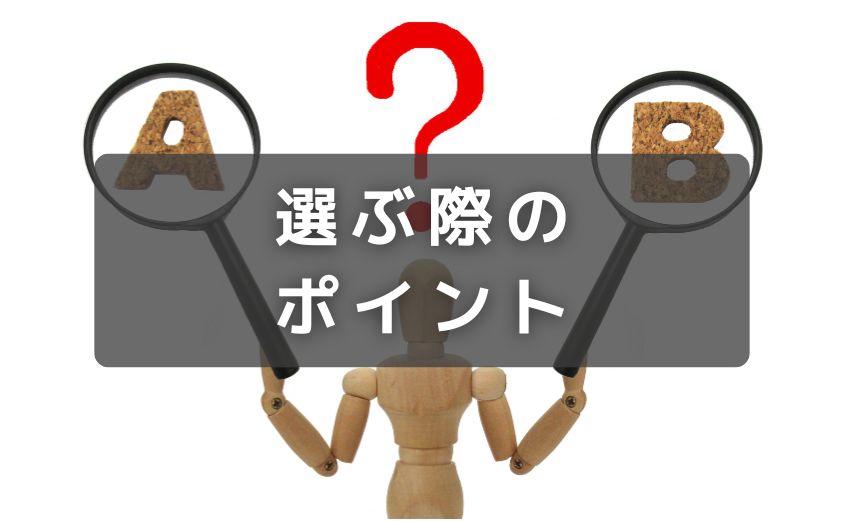
就労移行支援を効果的に活用するためには、自分に合った事業所を選ぶことが重要です。
事業所ごとに支援内容や雰囲気が異なるため、慎重に比較検討しましょう。



就労移行支援の事業所選びはとても大切です。
自分の目的に合った事業所を選びましょう。
- 事業所選びのチェックポイント
- 見学・体験利用のすすめ
事業所選びのポイントについて詳しく見ていきましょう。
6.1. 事業所選びのチェックポイント
就労移行支援事業所を選ぶ際は、いくつかのポイントをチェックすることで、自分に合った施設を見つけやすくなります。
以下のポイントを参考に、複数の事業所を比較してみましょう。
- 就職実績と就職率の確認(どれくらいの人が就職できているか)
- サポート内容が自分の目的に合っているか(スキル訓練や支援の充実度)
- 雰囲気やスタッフとの相性(通いやすい環境かどうか)
- 通いやすい立地・設備環境(自宅からの距離や設備の充実度)
- 利用者の口コミや評判(他の利用者の声を参考にする)
例えば、就職実績が高い事業所であれば、しっかりとした支援を受けられる可能性が高いです。
また、スタッフの対応や雰囲気が自分に合っているかどうかも、長く通うために重要なポイントになります。
事業所を選ぶ際は、見学や体験利用を活用して、実際の雰囲気を確認することをおすすめします。



就職実績やサポート内容を事前にチェックしましょう。
見学や体験利用を通じて、雰囲気を確認することも大切です。
次に、見学・体験利用の重要性について解説します。
6.2. 見学・体験利用のすすめ
就労移行支援事業所を選ぶ際は、見学や体験利用を活用することが大切です。
実際に訪れることで、雰囲気や支援内容が自分に合っているかを確認できます。
- 事前の見学や体験利用の重要性(実際の環境を知るため)
- 見学時のチェックポイント(設備やスタッフの対応を確認)
- 質問事項を準備する(疑問点を事前に整理しておく)
例えば、見学の際に「就職支援の具体的な内容」や「利用者の雰囲気」を確認することで、事業所が自分に合っているか判断しやすくなります。
また、体験利用では、実際にプログラムに参加し、訓練の進め方や支援の質を確かめることができます。
このように、見学や体験利用を通じて、納得のいく事業所選びをしましょう。



見学や体験利用を活用すると、事業所の雰囲気や支援内容を具体的に知ることができます。
事前に質問事項を準備しておくと、より有意義な見学になります。
次に、就労移行支援を利用するまでの流れについて解説します。
7. 就労移行支援を利用するまでの流れ


就労移行支援を利用するには、いくつかの手続きを経る必要があります。
事前に流れを把握しておくことで、スムーズに利用を開始できます。



就労移行支援の利用には、見学・相談・受給者証の申請などの手続きが必要です。
事前に流れを確認しておきましょう。
- 利用開始までの手続き
それでは、就労移行支援を利用するまでの具体的な手続きを詳しく見ていきましょう。
7.1. 利用開始までの手続き
就労移行支援を利用するには、いくつかの手続きを経る必要があります。
事前に流れを把握しておくことで、スムーズに利用を開始できます。
- 問い合わせ・相談(まずは事業所や自治体に相談)
- 見学・体験利用の申し込み(実際に雰囲気を確認する)
- 利用計画の作成(相談支援専門員とプランを立てる)
- 受給者証の申請(自治体で必要な手続きを行う)
- 通所開始の準備(事業所と通所スケジュールを調整)
例えば、まずは自治体の窓口や希望する事業所に問い合わせをし、相談することから始めます。
その後、事業所を見学・体験し、利用するかどうかを判断します。
正式に利用を決めたら、自治体に受給者証の申請を行い、許可が下り次第、通所を開始できます。



就労移行支援の利用には、受給者証の申請が必要です。
早めに手続きを進めるとスムーズに利用開始できます。
以上が、就労移行支援を利用するまでの流れです。
自分に合った事業所を選び、計画的に利用を進めましょう。
Q&A


- 就労移行支援とは?
-
就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すためのサポートを受けられる福祉サービスです。職業訓練や就職活動の支援を受けながら、スムーズな就職・定着を目指します。
- 就労移行支援の対象者は?
-
身体・知的・精神障害、発達障害、難病を持つ方が対象です。働くことに不安を感じる方や、職場での適応が難しい方が利用できます。
- 就労移行支援ではどんなトレーニングが受けられる?
-
ビジネスマナー、コミュニケーション能力の向上、PCスキルの習得、作業訓練、職業体験、自己理解やメンタルケアなど、働くために必要なスキルを学べます。
- 就職活動のサポート内容は?
-
履歴書・職務経歴書の作成支援、模擬面接、企業見学・実習、就労先の紹介、ハローワークの手続き支援など、就職に向けたサポートが受けられます。
- 就職後の定着支援はある?
-
職場での悩み相談、企業との調整、定期的な面談やフォローアップなど、就職後も安心して働き続けられるようサポートを受けられます。
- 就労移行支援の利用料金は?
-
基本的に無料ですが、世帯収入によっては自己負担が発生する場合があります。生活保護受給世帯や低所得世帯(住民税非課税)は無料で利用できます。
- 利用期間はどのくらい?
-
原則2年間ですが、特別な事情がある場合は延長が可能です。就職が決まると、利用期間内でもサービスが終了することがあります。
- 就労移行支援と就労継続支援の違いは?
-
就労移行支援は「一般企業への就職を目指す人向け」、就労継続支援は「一般就労が難しい人向けの福祉的な就労支援」です。継続支援にはA型(雇用契約あり)とB型(雇用契約なし)の2種類があります。
- 就労移行支援事業所の選び方は?
-
就職実績、支援内容、スタッフの対応、通いやすさ、設備環境、利用者の口コミなどを確認し、見学や体験利用を通じて自分に合った事業所を選びましょう。
- 利用を開始するまでの流れは?
-
①事業所や自治体へ問い合わせ → ②見学・体験利用 → ③利用計画の作成 → ④受給者証の申請 → ⑤通所開始、という流れで進めます。
まとめ


- 就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すための福祉サービス
- 職業訓練や就職活動のサポート、定着支援を受けられる
- 対象は身体・知的・精神・発達障害や難病の方で、原則2年間利用可能
- ビジネスマナーやPCスキル、自己理解など幅広いトレーニングを提供
- 利用料金は原則無料だが、世帯収入によって自己負担が発生する場合も
- 就労継続支援(A型・B型)とは目的や支援内容が異なる
- 事業所選びが重要!見学や体験利用を活用しよう
就労移行支援は、障害のある方が自分に合った職場で働くための準備をする大切なステップです。
無料で利用できる場合が多く、充実したサポートが受けられるので、就職に不安がある方はぜひ活用してみてください。



まずは気になる事業所の見学や体験利用をしてみましょう!