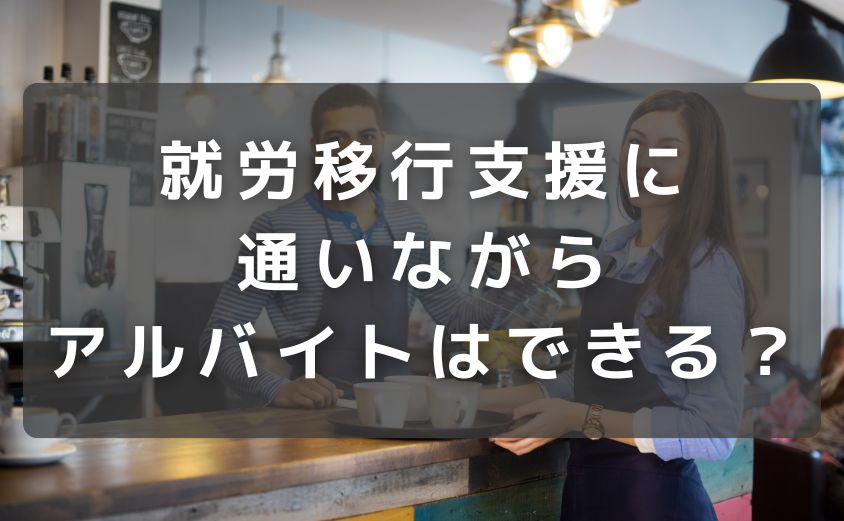就労移行支援とアルバイトは両立できる?収入と就職準備を両立する方法を解説!
「就労移行支援を利用したいけど、アルバイトも続けられるの?」
「収入がないと生活が厳しいけど、支援を受けながら働くことって可能?」
そんな疑問を抱えて、あなたはこのページにたどり着いたのではないでしょうか?
就労移行支援は、障害や体調に不安がある方の就職をサポートする制度ですが、利用中の収入について悩む人も少なくありません。特に、「完全にアルバイトを辞めるのは不安」「生活費を確保しながら就職の準備をしたい」と考える方にとって、 支援を受けながらアルバイトを続けることができるのか は大きな関心事ですよね。
結論から言うと、 就労移行支援とアルバイトは併用可能な場合があります! ただし、いくつかのポイントを押さえておかないと「思っていたより負担が大きかった」「支援の利用に影響が出た」といった問題が起こることも…。
実際にアルバイトを続けながら就職を成功させたAさんのストーリー
Aさんは「生活費のためにアルバイトを続けながら、就職活動も進めたい」と考えていました。就労移行支援の担当者と相談しながら、無理のない範囲でアルバイトを継続。その結果、 収入を確保しつつ就職準備も進めることができ、半年後に希望の職場に就職 することができました!
このように、 工夫次第でアルバイトと就労移行支援を両立し、スムーズに就職することは可能です!
この記事を読むと、こんなメリットがあります!
✅ アルバイトと就労移行支援を併用できる条件がわかる
✅ 収入面の不安を解消しながら就職準備を進める方法がわかる
✅ 実際に成功した人の事例を知り、自分に合った方法を見つけられる
✅ 注意すべきポイントを事前に知り、スムーズに両立できる
「アルバイトを続けながら就職を目指せるのか?」と不安に思っている方へ、この記事が解決のヒントになれば幸いです。あなたの状況に合った最適な方法を見つけて、無理なく就職に向かいましょう!
1. 就労移行支援とアルバイトの併用に関する基本情報
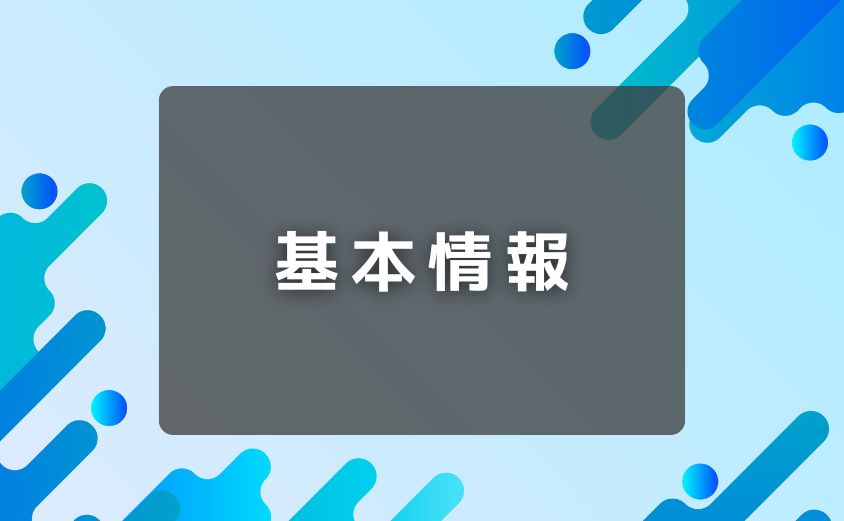
就労移行支援を利用しながらアルバイトをすることは、多くの人が気になるテーマです。
就労移行支援には一定のルールがあり、アルバイトとの併用には注意が必要です。

就労移行支援とアルバイトの両立には制約があります。
ルールを理解して、適切な選択をしましょう。
- 就労移行支援の概要
- アルバイトの種類
就労移行支援とは、障がいや体調の問題がある人が一般就労を目指すためのサポートを受けられる制度です。
一方、アルバイトは生活費を補う手段として重要ですが、就労移行支援との併用にはルールがあります。
1.1. 就労移行支援とは
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障がい者のための支援サービスです。
国が定める福祉サービスの一つで、一定期間、専門的な訓練やサポートを受けながら就職活動を行えます。
- 職業訓練を提供
- 履歴書や面接のサポート
- 企業実習の機会がある
たとえば、発達障害のある方がコミュニケーションスキルを学びながら、企業実習を通じて働く準備を整えることができます。
就労移行支援を利用することで、安心して自分に合った職場を見つける手助けが受けられます。
就職に向けてサポートを受けられる点が、就労移行支援の最大のメリットです。
1.2. アルバイトの定義と種類
アルバイトとは、正社員や契約社員ではなく、短期間やシフト制で働く雇用形態のことを指します。
働く時間や雇用期間によって、いくつかの種類に分かれます。
- 長期アルバイト
- 単発アルバイト
- 副業
たとえば、飲食店でのホールスタッフとして長期アルバイトをする人もいれば、イベントスタッフとして単発で働く人もいます。
また、本業の収入を補うために、副業としてアルバイトを選ぶ人もいます。
自分の生活スタイルや就労移行支援のルールに合わせて、適切な働き方を選ぶことが大切です。



アルバイトにはさまざまな種類があり、就労移行支援と両立しやすいものもあります。
自分に合った働き方を選びましょう。
2. 就労移行支援利用中のアルバイトに関する規則
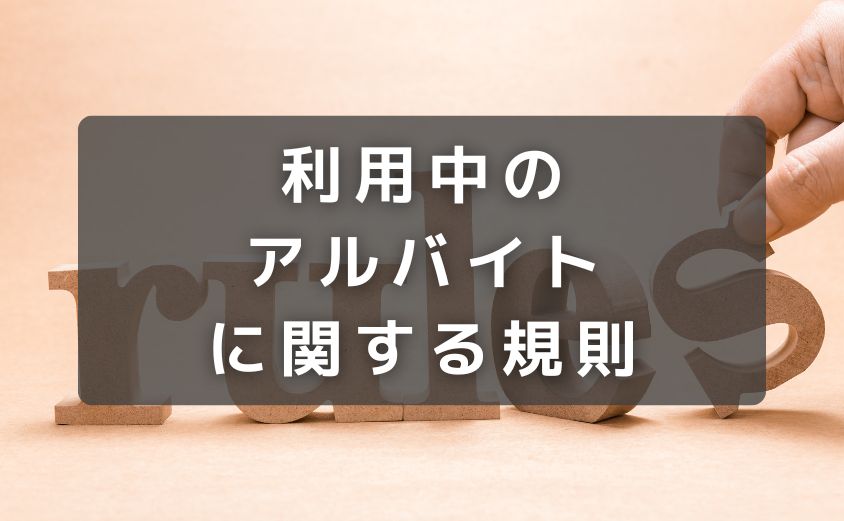
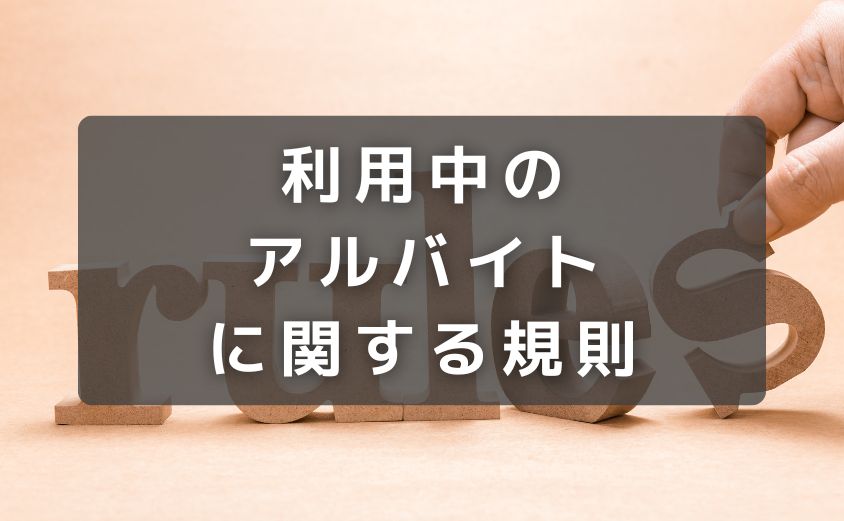
就労移行支援を利用しながらアルバイトをすることには、法律や自治体のルールがあります。
原則としてアルバイトは禁止されていますが、特定の条件下では認められるケースもあります。



就労移行支援中のアルバイトは基本的に禁止です。
しかし、例外的に認められるケースもあります。
- 厚生労働省の見解
- 自治体や事業所の対応
厚生労働省は、就労移行支援を受けている間のアルバイトを基本的に認めていません。
しかし、自治体や事業所によっては、一定の条件を満たせば例外的に許可される場合があります。
2.1. 厚生労働省の見解
厚生労働省は、就労移行支援の目的を「一般就労の準備」としており、アルバイトはこれに影響を与えるため禁止されています。
そのため、多くの事業所では、利用者がアルバイトをすることを認めていません。
- 就労移行支援の目的は就職準備
- アルバイトは原則禁止
- 利用者の負担増加を懸念
たとえば、就労移行支援の訓練が終わった後にアルバイトを入れると、疲れがたまり支援の効果が薄れる可能性があります。
また、アルバイトが優先されてしまうと、支援の本来の目的である就職活動が疎かになる恐れもあります。
そのため、基本的にはアルバイトは禁止されているのです。
2.2. 自治体や事業所の対応
自治体や事業所ごとに、アルバイト併用のルールは異なります。
一部の自治体では、生活困窮などの理由があれば、一定の範囲でアルバイトが認められることもあります。
- 自治体ごとに異なるルール
- 一部の事業所では例外的に許可
- アルバイト可能な時間の制限あり
たとえば、ある自治体では「週10時間以内のアルバイトは認める」といったルールを設けている場合があります。
また、事業所の方針によっては、「事前に相談すれば許可する」ケースもあるようです。
アルバイトを考えている場合は、まず事業所や自治体の担当者に相談することが大切です。



私が住んでいた自治体は事前相談をすることでアルバイトの許可が下りるところでした。
アルバイトをしてみて思ったのは隠れながらするのは、かなり心身ともに負荷があるので難しいと思います。



自治体や事業所ごとにルールが異なるため、必ず事前に確認しましょう。
勝手にアルバイトを始めると、支援を受けられなくなる可能性があります。
3. アルバイト併用が認められる可能性と条件
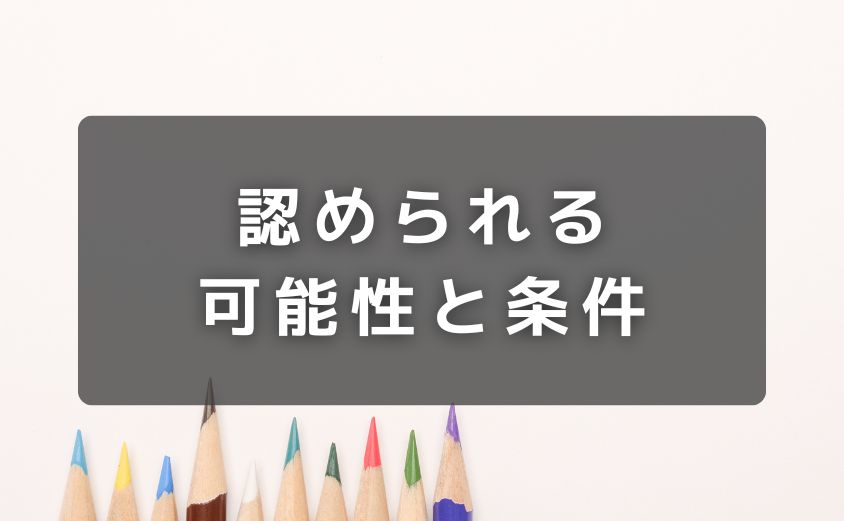
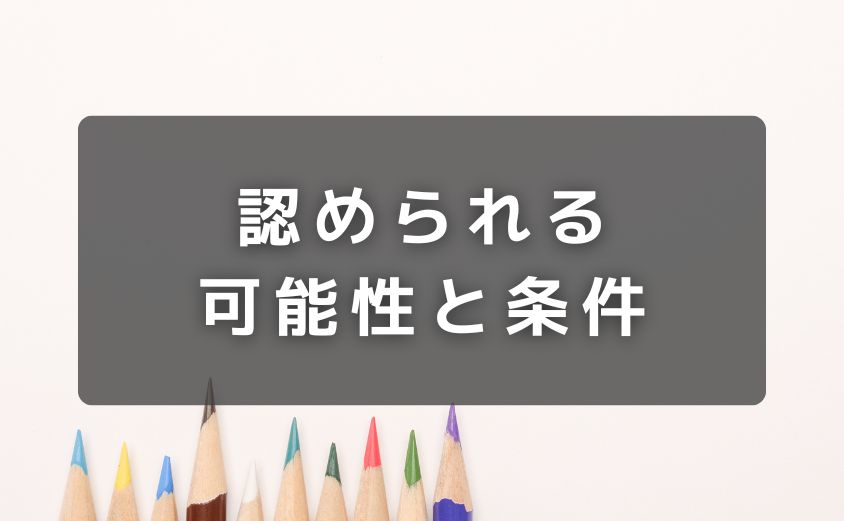
就労移行支援中のアルバイトは基本的に禁止されていますが、特定の条件を満たせば例外的に認められることがあります。
生活の困窮や就労のステップアップを目的とした場合、一部の自治体や事業所が許可を出すケースもあります。



特定の条件を満たせば、アルバイトが認められる可能性があります。
まずは事業所や自治体に相談しましょう。
- 例外的に認められるケース
- 許可を得るための手続き
アルバイト併用が認められるかどうかは、ケースバイケースです。
事業所や自治体に相談し、必要な手続きを踏むことが重要です。
3.1. 例外的に認められるケース
アルバイトが例外的に認められるケースとして、生活費の困窮や就職後のステップアップが挙げられます。
ただし、週の労働時間や仕事内容には一定の制限が設けられることが多いです。
- 生活費が不足している場合
- 週20時間以内のアルバイト
- 就職活動の一環としての仕事
たとえば、一人暮らしで生活が苦しく、最低限の生活費を確保するためにアルバイトが必要な場合、許可が出る可能性があります。
また、実際に働くことで就職への準備をしたい場合も、事業所の判断によっては認められることがあります。
事前に相談し、適切な手続きを踏むことが大切です。
3.2. 許可を得るための手続き
アルバイトを希望する場合、まずは事業所や自治体に相談し、正式な許可を得る必要があります。
勝手にアルバイトを始めると、就労移行支援の利用停止やサービス費の返還を求められる可能性があるため、必ず手続きを踏みましょう。
- 事業所の担当者に相談
- 自治体に申請
- 許可が下りるまでアルバイトをしない
たとえば、ある自治体では「生活費の困窮を証明する書類」を提出することでアルバイトが許可される場合があります。
また、事業所の判断によっては「週10時間以内の短時間アルバイト」に限り認められることもあります。
アルバイトを希望する場合は、事業所のルールを確認し、適切な手続きを行いましょう。
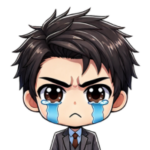
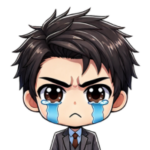
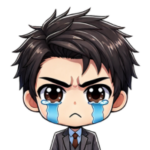
アルバイトをする前に、必ず事業所や自治体に相談しましょう。
体調を崩して本調子になるまでの間に無理をすると、その無理した分、自分にかえってきてしまう可能性があります。
まずは自分を大事にしてあげてください。
4. アルバイト併用が発覚した場合のリスク


就労移行支援を利用しながらアルバイトをしていることが発覚すると、さまざまなリスクが発生します。
最悪の場合、就労移行支援の利用停止やサービス費の返還を求められる可能性があります。



無許可のアルバイトが発覚すると、就労移行支援が利用できなくなることも。
リスクを理解し、慎重に判断しましょう。
- 就労移行支援の利用停止
- 事業所への影響
アルバイトが発覚すると、利用者本人だけでなく、事業所にも影響を及ぼすことがあります。
規則違反によって支援を受けられなくなる可能性があるため、慎重に行動しましょう。
4.1. 就労移行支援の利用停止
無許可でアルバイトをすると、就労移行支援の利用を停止される可能性があります。
また、場合によっては、過去に受けた支援の費用を返還するよう求められることもあります。
- 利用停止になる可能性
- サービス費の返還請求
- 今後の福祉サービス利用に影響
たとえば、無許可のアルバイトが発覚し、自治体からサービスの利用停止を通知されるケースもあります。
また、支援を受ける際に虚偽の申告をしていたと判断されると、今後の福祉サービス利用が難しくなることもあります。
そのため、ルールを守り、事前に相談することが重要です。
4.2. 事業所への影響
利用者が無許可でアルバイトをしていたことが発覚すると、事業所にも影響を与える可能性があります。
場合によっては、事業所の運営に対して行政指導が入り、最悪の場合、運営停止となることもあります。
- 事業所の信用低下
- 行政指導や罰則の可能性
- 他の利用者への影響
たとえば、自治体の監査で利用者の無許可アルバイトが発覚し、事業所が厳しい指導を受けることがあります。
これにより、他の利用者にも影響が及び、サービスの提供が制限される可能性もあります。
自分だけの問題ではなく、周囲にも迷惑がかかることを理解しておきましょう。



アルバイトが発覚すると、事業所にも影響が出ます。
事業所の信用を守るためにも、ルールを守ることが大切です。
5. アルバイトがバレる主な理由


就労移行支援を利用しながら無許可でアルバイトをすると、思わぬ形で発覚することがあります。
特に、税金や保険の記録、通所状況の変化が原因でバレるケースが多いです。



アルバイトは思わぬ形でバレることがあります。
税金や通所状況の変化には注意が必要です。
- 収入の申告
- 通所状況の変化
特に、住民税の通知や体調の変化によって、アルバイトが発覚するケースが多いです。
事業所や自治体はさまざまな方法でチェックしているため、慎重に行動する必要があります。
5.1. 収入の申告
アルバイトをしていると、税金や保険の記録に影響が出るため、収入の申告でバレることがあります。
特に、住民税の増加や所得税の控除がきっかけで発覚するケースが多いです。
- 住民税の通知で発覚
- 健康保険の記録に影響
- 扶養控除の変更
たとえば、自治体が住民税の課税通知を送る際、前年よりも収入が増えていると事業所に報告されることがあります。
また、扶養控除の変更が会社に通知され、雇用主を通じてバレることもあります。
このように、税金や保険の制度によってアルバイトが発覚するケースが多いため注意が必要です。
5.2. 通所状況の変化
アルバイトを始めると、通所状況に変化が出ることがあり、それが発覚の原因になることがあります。
特に、遅刻や欠席が増えたり、体調を崩しやすくなったりすると、事業所に疑われる可能性があります。
- 遅刻や欠席の増加
- 疲れや体調不良の頻発
- 通所態度の変化
たとえば、深夜のアルバイトを始めたことで朝の通所が難しくなり、頻繁に遅刻するようになると、事業所に疑われる可能性があります。
また、アルバイトによる疲労が原因で訓練に集中できなくなると、支援の質が低下することもあります。
このような変化が続くと、事業所のスタッフが「アルバイトをしているのでは?」と疑い、発覚することにつながります。



アルバイトによる通所状況の変化は、事業所に気づかれやすいポイントです。
規則を守ることが大切です。
6. 生活費の確保に利用できる制度


就労移行支援を利用している間、収入がないことに不安を感じる人も多いでしょう。
しかし、公的な支援制度を活用すれば、生活費を確保することが可能です。



生活費の不安がある場合、公的支援を活用しましょう。
いくつかの制度を組み合わせることで負担を軽減できます。
- 公的支援制度
- 相談窓口の活用
生活費の支援には、傷病手当金や障害年金などの制度があります。
また、専門の相談窓口を利用することで、適切な支援を受けることも可能です。
6.1. 公的支援制度
就労移行支援を利用する間、生活費を補うために活用できる公的支援制度があります。
主に、傷病手当金、失業保険、障害年金、生活保護などが利用可能です。
- 傷病手当金
- 失業保険
- 障害年金
- 生活保護
たとえば、うつ病などの理由で仕事を辞めた場合、傷病手当金を申請すれば、一定期間の生活費を確保できます。
また、障害年金を受給できるケースもあるため、まずは自治体や専門機関に相談しましょう。



私の場合は、担当していただいた支援員さんからしてもらった提案に生活保護を受給しながらの通所がありました。
色んな制約はありますが、一定期間の生活費を確保する方法はあります。
そのためにも、どんな方法があるか各自治体によって違うため、相談することが大切です。
6.2. 相談窓口の活用
生活費の支援については、専門の相談窓口を活用することで適切なアドバイスを受けられます。
特に、障がい者就業・生活支援センターや自立相談支援機関が有益な情報を提供してくれます。
- 障がい者就業・生活支援センター
- 自立相談支援機関
たとえば、障がい者就業・生活支援センターでは、就労支援と合わせて生活費の相談も可能です。
困ったときは、一人で悩まずに専門機関に相談することをおすすめします。



生活費に不安がある場合は、公的支援や相談窓口を活用しましょう。
一人で悩まず、専門機関に相談することが大切です。
私は悩みのままで終わらせず、相談することで自分にあった可能性を探すことが心を軽くしていくことができました。
7. 就労移行支援と併用可能なサービス
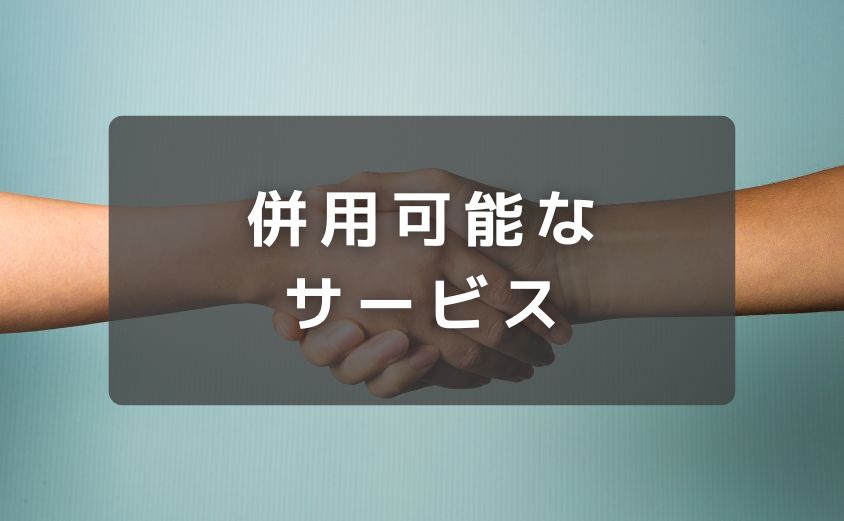
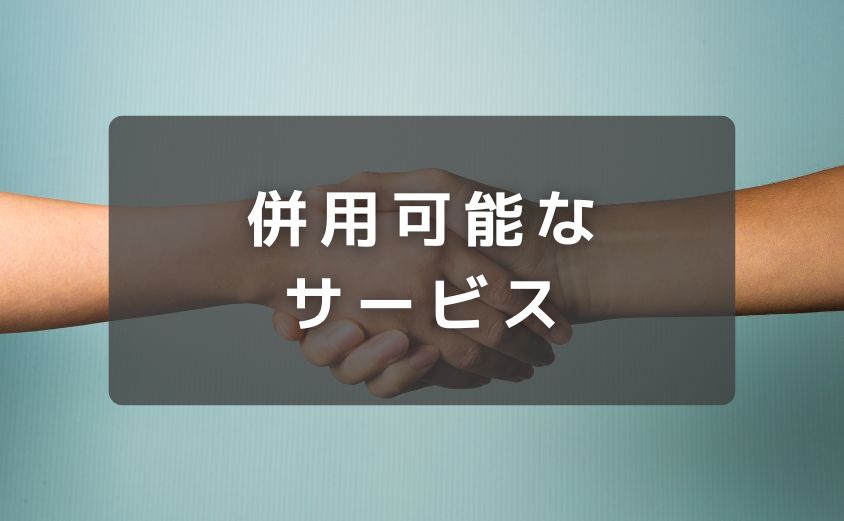
就労移行支援を利用しながら、他の福祉サービスを併用することも可能です。
特に、障がい者グループホームや生活介護サービスは、生活の安定を支援する制度として役立ちます。



就労移行支援と併用できるサービスがあります。
生活を安定させるために、積極的に活用しましょう。



アパートタイプや一軒家で共に過ごすシェアタイプもありますよ。
事業所の支援員さんや自治体に相談しながら、情報を集めましょう。
- 障がい者グループホーム
- 生活介護サービス
住環境や日常生活の支援を受けることで、よりスムーズに就職を目指せるようになります。
事業所や自治体の支援窓口に相談し、適切なサービスを活用しましょう。
7.1. 障がい者グループホーム
障がい者グループホームは、日常生活の支援を受けながら共同生活ができる施設です。
就労移行支援と併用することで、生活の安定を図りながら就職活動に集中できます。
- 生活支援が受けられる
- 家賃補助がある場合も
- 就職後も利用可能
たとえば、食事の準備や金銭管理のサポートを受けながら、安心して訓練に取り組めます。
また、一定の条件を満たせば家賃補助を受けられる場合もあります。
自立した生活を目指しながら、就労移行支援を活用するための選択肢の一つです。
7.2. 生活介護サービス
生活介護サービスは、障がいのある方が日中の支援を受けられる福祉サービスです。
就労移行支援と併用しながら、自分のペースで働く準備ができます。
- 日常生活の支援を受けられる
- 体調管理のサポート
- リハビリや軽作業も可能
たとえば、就労に向けて体調を整えるために、生活介護サービスでリハビリを受けながら訓練を行うこともできます。
また、事業所によっては、軽作業を行いながら少しずつ働く準備をすることも可能です。
自分の体調や状況に応じたサポートを受けることで、就職へのステップを踏みやすくなります。



生活介護サービスを活用することで、体調管理をしながら働く準備ができます。
無理なく就職を目指しましょう。
8. 就労移行支援利用中の注意点


就労移行支援を最大限に活用するためには、利用中の注意点を理解しておくことが大切です。
特に、通所を優先することや収入と支出のバランスに気を配ることが重要になります。



就労移行支援を受ける際は、通所の優先度や収入面に注意しましょう。
しっかり活用して、スムーズな就職を目指してください。
- 通所の優先順位
- 収入と支出のバランス
就職を成功させるためには、支援を十分に活用し、安定した環境で訓練に取り組むことが大切です。
経済的な不安がある場合は、公的支援制度なども併用しながら計画的に利用しましょう。
8.1. 通所の優先順位
就労移行支援を利用する際は、まず通所を最優先することが大切です。
通所を疎かにしてしまうと、支援の効果が十分に得られず、就職活動に悪影響を及ぼす可能性があります。
- アルバイトより通所を優先
- 訓練やプログラムに積極的に参加
- 体調管理をしながら継続
たとえば、無理にアルバイトを入れてしまい、疲労やストレスで通所ができなくなると、支援の効果が半減してしまいます。
通所を続けることでスキルが身につき、企業実習や就職の機会が広がるため、安定した生活リズムを意識しましょう。



アルバイト選びはすごく大切です。
時給だけ見るのではなく、通いやすさやシフトの組みやすさも確認しましょう。
私は土日祝含む週1~3回まで。時間は3時間からOKのアルバイトを探して、働いていました。
8.2. 収入と支出のバランス
就労移行支援を受ける際は、収入と支出のバランスを考え、計画的に生活することが重要です。
特に、就労移行支援の利用料や交通費、生活費などを把握し、無理のない資金計画を立てることが求められます。
- 就労移行支援の利用料を確認
- 収入増加による影響を考慮
- 公的支援制度の活用
たとえば、アルバイトの収入が一定額を超えると、障害年金や生活保護の支給額に影響が出ることがあります。
また、就労移行支援の利用料が発生する場合もあるため、事前に確認し、無理のない範囲で生活設計を立てることが大切です。



就労移行支援を有効に活用するためには、通所を優先し、収入と支出のバランスを考えることが大切です。
支援を受けながら計画的に生活しましょう。
Q&A


- 就労移行支援を利用しながらアルバイトはできる?
-
基本的に、就労移行支援を利用しながらのアルバイトは原則禁止されています。ただし、自治体や事業所の判断によっては、生活困窮などの理由で例外的に許可されるケースもあります。
- 就労移行支援の目的とは?
-
就労移行支援は、障がいや体調の問題がある方が一般企業への就職を目指すための支援サービスです。職業訓練や履歴書・面接のサポート、企業実習の機会などを提供し、スムーズな就職を支援します。
- アルバイトが例外的に認められる条件は?
-
生活費の困窮や就職へのステップアップが目的である場合、一部の自治体や事業所でアルバイトが認められる可能性があります。許可を得るには、事前に事業所や自治体の担当者に相談し、正式な手続きを踏むことが必要です。
- 無許可でアルバイトをした場合のリスクは?
-
無許可でアルバイトをすると、就労移行支援の利用停止や、過去に受けた支援費用の返還を求められる可能性があります。また、事業所にも影響を与え、運営に対する行政指導が入る場合もあるため、注意が必要です。
- アルバイトがバレる原因は?
-
主な原因として、住民税の通知や健康保険の変更、通所状況の変化(遅刻・欠席の増加、体調不良の頻発)などが挙げられます。税金や社会保険の記録は行政が管理しているため、意図せず発覚するケースが多いです。
- 生活費の確保に利用できる制度は?
-
就労移行支援を利用している間は、傷病手当金、失業保険、障害年金、生活保護などの公的支援制度を活用できます。生活費に不安がある場合は、自治体や専門の相談機関に相談しましょう。
- 就労移行支援と併用できるサービスは?
-
障がい者グループホームや生活介護サービスなどが併用可能です。グループホームでは生活支援が受けられ、生活介護サービスではリハビリや軽作業を通じて就職の準備ができます。
- 就労移行支援を有効に活用するためのポイントは?
-
通所を最優先し、訓練やプログラムに積極的に参加することが大切です。また、収入と支出のバランスを考え、公的支援制度を活用しながら計画的に生活することが、スムーズな就職につながります。
まとめ


- 就労移行支援中のアルバイトは基本的に禁止されている
- 一部の自治体や事業所では、特定の条件下で例外的に認められることもある
- 無許可でアルバイトをすると、支援の利用停止や費用の返還請求が発生する可能性がある
- アルバイトが発覚する主な要因は税金の記録や通所状況の変化
- 生活費の不安がある場合は、公的支援制度の活用を検討する
- 就労移行支援を最大限に活用するためには、通所を最優先し、計画的に生活をすることが大切
就労移行支援を利用する際は、ルールを守りながら適切な選択をすることが重要です。
生活費の不安がある場合は、アルバイトではなく、公的支援や他の福祉サービスの活用を検討してみましょう。



お金も大切ですが、自分のことをもっと大切にしてください。
そのうえで、就労移行支援を活用して、無理のない形で就職を目指しましょう。
支援制度や相談窓口について詳しく知りたい方は、自治体や専門機関に問い合わせてみてください。