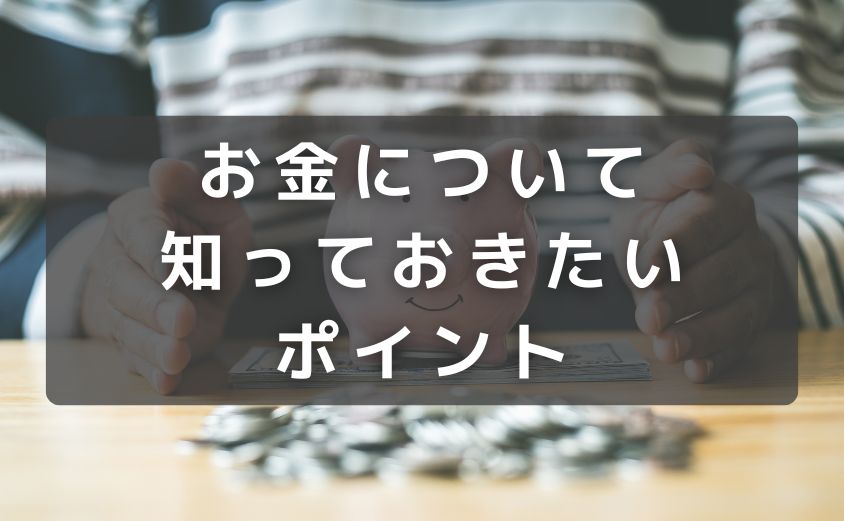「就労移行支援を利用したいけれど、お金がなくて迷っている…。」そんな悩みを抱えていませんか?就労移行支援は、就職を目指す方にとって大きな支えとなるサービスですが、「費用が高いのでは?」という不安が頭をよぎり、一歩を踏み出せずにいる方も多いようです。しかし、実は多くの場合、経済的な負担を気にせず利用できる方法が用意されています。
この記事では、「就労移行支援を受けたいけれどお金がない」というあなたに寄り添い、具体的な解決策をわかりやすくお伝えします。
たとえば、就労移行支援は基本的に障害者総合支援法に基づき運営されているため、条件を満たせば自己負担額が無料または軽減される仕組みがあることをご存じですか?
この記事では、この仕組みを詳しく解説するとともに、実際に経済的なハードルを乗り越えて支援を受けた人の成功事例をご紹介します。
かつて経済的に苦しい状況にあったAさんも、この記事で紹介する制度を活用して費用の心配を解消。その結果、希望していた職場に就職し、安定した収入を得られるようになりました。「お金がない」という壁を乗り越えたことで、生活に自信を取り戻し、将来への希望を感じられるようになったそうです。
さらにこの記事を読むと、次のようなメリットが得られます:
- 就労移行支援を無料または低額で利用するための具体的な手続きや条件がわかる
- 自分が利用可能な支援制度を調べる方法がわかる
- 就労移行支援を通じて得られるスキルや経験が理解できる
「お金がないから諦めるしかない」と感じている今の状況を変えるヒントが、このページには詰まっています。経済的な理由で迷っているあなたの背中を押すために、実際に支援を受けた人々の声やリアルな体験談も交えて解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
この記事をきっかけに、あなたが就職への新しい一歩を踏み出せることを願っています。
移行就労支援利用時にかかる費用
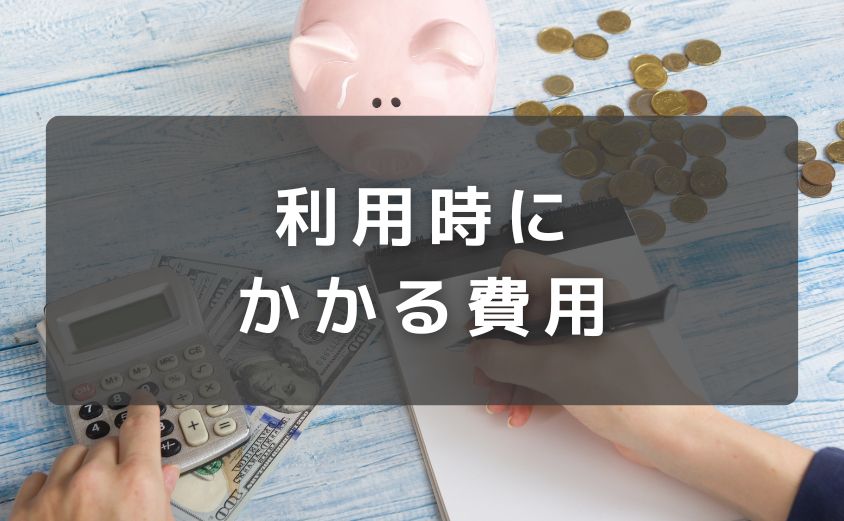
移行就労支援を利用する際には、利用者が負担する費用があります。
ただし、負担額は世帯収入や個人の状況に応じて異なります。

移行就労支援の利用料金は収入に応じて異なります。
収入が少ない人は負担が軽減されます。
- 利用料金の負担上限額
- その他の費用
ここでは利用料金の仕組みや、移行就労支援を利用する際にかかるその他の費用について詳しく解説します。
また、実際にかかる金額についても具体的に説明していきます。
利用料金の負担上限額
移行就労支援の利用料金は、世帯の所得状況に応じて負担上限額が設定されています。
これにより、低所得世帯や生活保護を受けている人にとって負担が少ない仕組みになっています。
- 生活保護世帯・住民税非課税世帯:0円
- 住民税課税世帯(所得16万円未満):9,300円
- それ以上の所得の場合:37,200円
たとえば、住民税が非課税の世帯であれば、利用料金がかからないため安心です。
一方で、所得が高い場合は月額で37,200円の負担が必要になります。
負担上限額は自治体によって多少異なる場合があるため、必ず事前に確認してください。
利用料金を理解することで、予算を組みやすくなります。
その他の費用
移行就労支援を利用する際には、利用料金以外にもいくつかの費用が発生する場合があります。
具体的には、交通費や食事代などの個人的な出費が含まれます。
- 交通費:自宅から事業所や企業見学への移動費
- 食事代:昼食、飲み物、間食などの費用
たとえば、事業所まで公共交通機関を使う場合、その往復分の交通費がかかります。
また、事業所内で昼食をとる場合には、弁当代や飲み物の費用も考慮が必要です。
費用は人それぞれ異なりますが、月々の支出を事前に見積もることが重要です。
事業所によっては、交通費の補助制度を利用できる場合もありますので確認してみましょう。



移行就労支援の利用では、交通費や食事代がかかることを忘れないでください。
移行就労支援利用中の収入源


移行就労支援を利用中の収入源は、主に公的な制度や家族からの支援に頼る形となります。
この期間はアルバイトなどの収入を得ることが難しいため、他の収入源を確保することが大切です。



移行就労支援中の収入源は限られています。
障害年金や生活保護の活用が鍵です。
- 障害年金
- 雇用保険の基本手当(給付金)
- 傷病手当金
- 生活保護
- 家族からの援助
ここでは、移行就労支援中の主な収入源について詳しく説明します。
各収入源の受給条件や金額の目安もあわせて確認しておきましょう。
障害年金
障害年金は、障害を持つ人が生活を安定させるために受け取れる公的な収入源です。
主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、受給には一定の条件があります。
- 障害基礎年金:国民年金加入者が対象
- 障害厚生年金:厚生年金加入者が対象
- 受給には障害の程度に応じた判定が必要
- 過去の保険料納付状況も条件に含まれる
たとえば、障害基礎年金は障害の程度が1級の場合、年間約97万円を受給できます。
また、2級の場合は年間約78万円が支給されます。
障害厚生年金は、加入期間や給与額によって受給額が異なる点が特徴です。
申請には診断書や必要書類が求められるため、早めに準備を進めましょう。
雇用保険の基本手当(給付金)
雇用保険の基本手当(給付金)は、離職後に一定期間受け取れる収入源です。
特に就職困難者として認定された場合、受給期間が通常よりも延長される場合があります。
- 離職後に申請が必要
- 基本手当は賃金日額の50~80%が支給
- 就職困難者の場合、最大1年間の受給が可能
- 受給条件は過去2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入
たとえば、離職時の年齢が45歳以上の場合、基本手当の支給期間は最大330日間です。
就職困難者と認定された場合、さらに延長されることがあります。
申請はハローワークで行い、支給までに一定の審査期間が必要です。
雇用保険を活用することで、生活費を安定させながら就労移行支援を利用できます。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険に加入している人が病気やケガで働けなくなった場合に受け取れる給付金です。
給与の減少を補う形で支給され、一定の条件を満たす必要があります。
- 健康保険加入が条件
- 給与の3分の2が支給される
- 最長で1年6ヶ月間の支給が可能
- 支給には診断書の提出が必要
たとえば、月収30万円の場合、傷病手当金として20万円が支給されます。
この制度は収入の減少を防ぎ、治療に専念できる環境を提供します。
申請には会社からの証明書と医師の診断書が必要です。
傷病手当金を活用することで、就労移行支援中の生活費を補えます。
生活保護
生活保護は、生活に困窮している人が最低限の生活を保障される制度です。
食費や住宅費、医療費など、生活の基本を支えるために支給されます。
- 収入が基準額を下回る場合が対象
- 医療費は全額負担されない
- 家賃補助も支給される
- 自治体の窓口で申請
たとえば、単身者の場合、基準額は地域によって異なりますが月6万円程度です。
生活保護を受けると、医療費や家賃の負担も軽減されます。
就労移行支援中に生活費が不足する場合、自治体の福祉課で相談しましょう。
この制度は生活の安定を図るための最後の手段として活用できます。
家族からの援助
家族から生活費の援助を受けることは、就労移行支援に集中するための手段となります。
特に、制度だけでは補えない場合に頼りやすい方法です。
- 生活費や交通費の補助
- 食材や日用品の提供
- 精神的なサポートも期待
- 制度利用までの一時的な支援
たとえば、親や兄弟からの支援で家賃や食費を一部負担してもらうケースがあります。
生活費の一部を負担してもらうことで、経済的な不安を軽減できます。
また、家族の支援は精神的な励みとなり、利用者の自立を後押しします。
家族との話し合いを通じて、どの程度の支援が可能か明確にしておきましょう。



移行就労支援中は、家族の援助が大きな助けになります。
話し合いをして支援を受けましょう。
生活費のサポートとなる制度や相談先
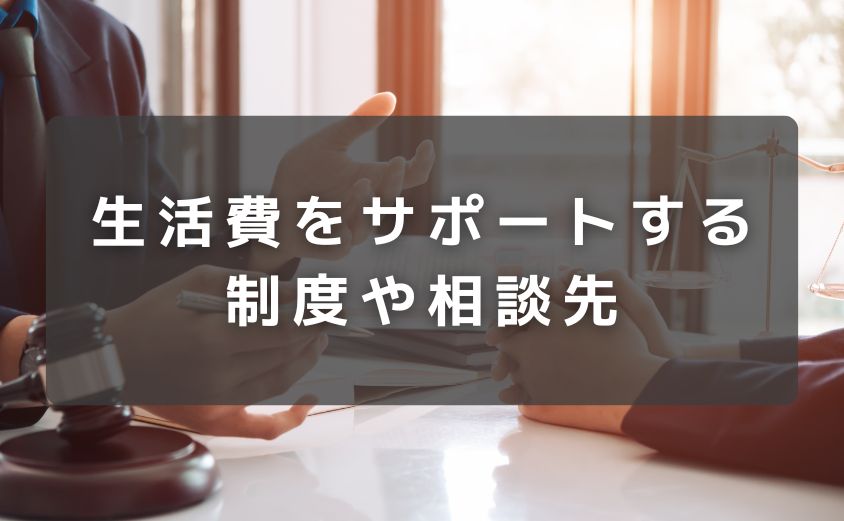
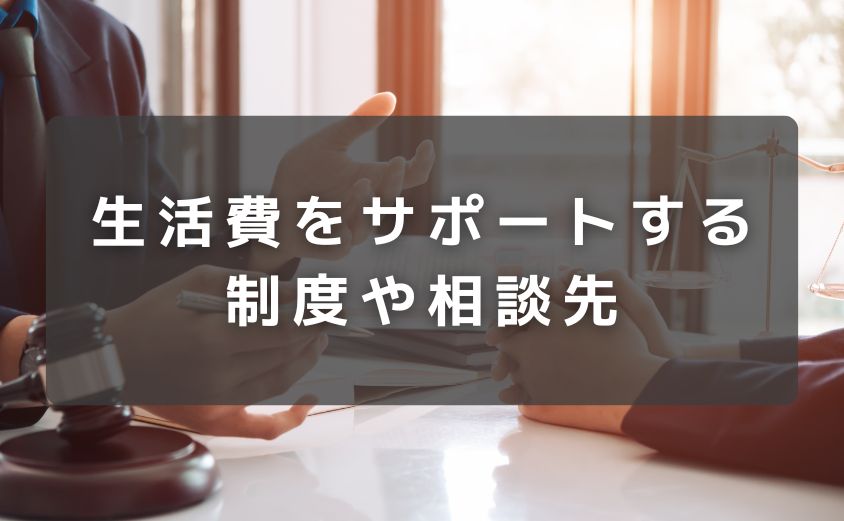
移行就労支援を利用中、生活費のサポートとなる制度を活用することが重要です。
また、生活費に関する相談ができる窓口を利用することで、不安を軽減できます。



生活費をサポートする制度や相談先があります。
困ったときは、まず相談を。
- 自立支援医療制度
- 障害者手帳
- 自治体の制度
- 相談する
ここでは、利用可能な主な制度と相談先について詳しく解説します。
これらを活用することで、移行就労支援利用中の生活費負担を軽減できます。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、障害の治療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度です。
障害を持つ人が、必要な治療を受けやすくするための支援策となっています。
- 医療費の自己負担が原則1割
- 所得に応じて負担上限額が設定
- 精神疾患、身体疾患などが対象
- 申請は市区町村の福祉課で行う
たとえば、通院で1回あたりの医療費が1万円かかる場合、この制度を利用すると1,000円程度に軽減されます。
さらに、所得による負担上限額があるため、低所得世帯では月額数千円の負担で済むことが多いです。
申請には診断書や申請書が必要なため、主治医や自治体窓口で相談しましょう。
この制度を活用すれば、医療費負担を大幅に軽減し、生活費のやりくりがしやすくなります。
障害者手帳
障害者手帳を持つことで、さまざまな特典や割引を受けられます。
生活費の負担を減らすためにも、早めに申請することをおすすめします。
- 税金の減免措置
- 公共交通機関の割引
- 公的施設の利用料が無料または割引
- 携帯料金の割引プランも利用可能
たとえば、電車やバスの運賃が半額になる地域もあります。
また、市区町村が運営するスポーツ施設や図書館の利用料が無料になることもあります。
手帳を取得するためには、医師の診断書や写真、必要書類の提出が必要です。
障害者手帳は金銭的な負担軽減だけでなく、日常生活をより便利にするための手段です。
次に、「自治体の制度」と「相談する」の部分を作成します。
自治体の制度
自治体独自で提供される支援制度を活用することで、生活費の負担をさらに軽減できます。
各地域の福祉課や相談窓口で詳細を確認することをおすすめします。
- 交通費や訓練費の補助
- 生活必需品の提供や貸付制度
- 障害者向けの就労支援サービス
- 地域特有の割引や助成制度
たとえば、通勤や通所にかかる交通費を自治体が一部負担してくれる場合があります。
また、特定の条件を満たせば、家賃補助や就労支援のための助成金が利用できる地域もあります。
申請条件や手続きは自治体ごとに異なるため、事前に問い合わせておきましょう。
自治体の制度を利用することで、経済的負担を軽減し、安心して支援を受けられる環境を整えられます。
相談する
生活費に関する不安がある場合、専門の相談機関を利用することが重要です。
支援のプロと話すことで、自分に合った解決策を見つけることができます。
- 障害者意思決定・生活支援センター
- 自立相談支援機関
- 社会福祉協議会
- 地域包括支援センター
たとえば、「障害者意思決定・生活支援センター」では、生活全般や就労についての相談が可能です。
また、「自立相談支援機関」では、生活費のやりくりに関する具体的なアドバイスを受けられます。
相談することで、生活費に関する新たな支援制度や利用可能な補助金の情報が得られることもあります。
不安を感じたら一人で悩まず、まずは専門家に相談することが大切です。



自治体や相談機関を活用すれば、生活費の不安を減らせます。
積極的に相談してみましょう。
生活費を守るためにできること
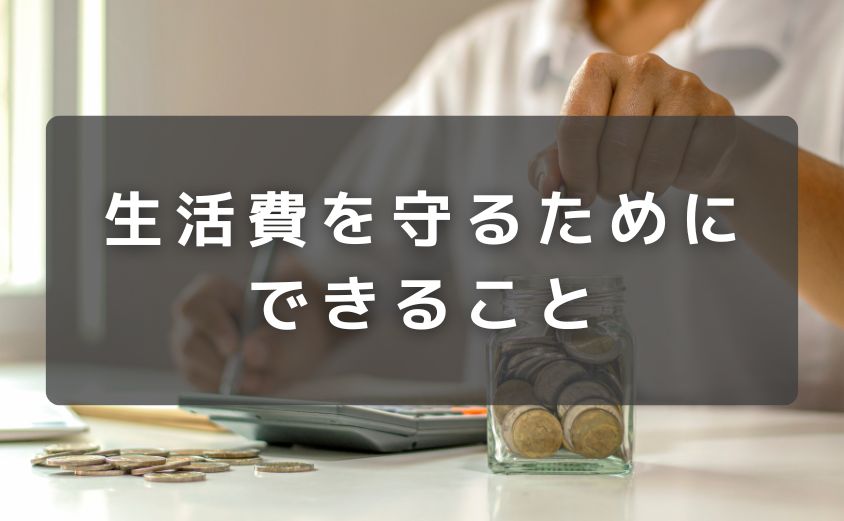
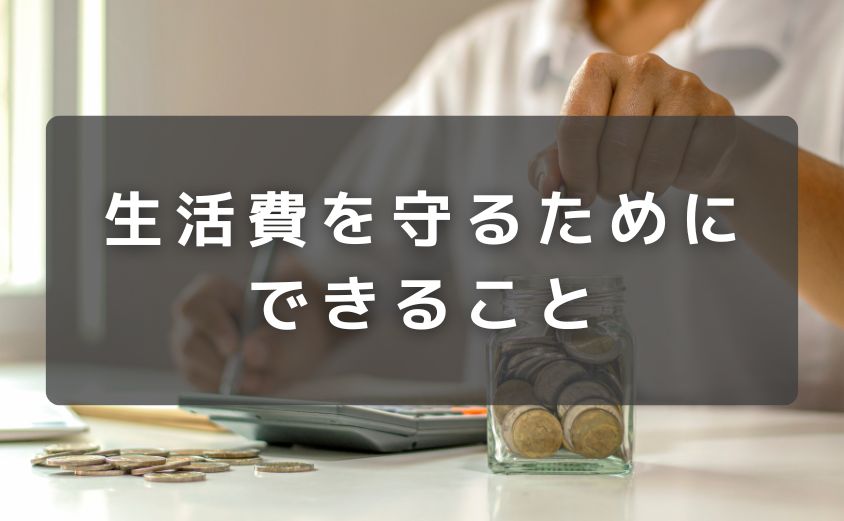
就労移行支援を利用中は、収入が限られるため生活費を効率的に管理することが重要です。
利用できる制度を活用したり、節約を工夫することで、生活費を守ることができます。



生活費を守るには、支援制度や節約の工夫が必要です。
無理なくできる方法を見つけましょう。
- 自立支援医療制度の活用
- 障害者手帳の取得
- 日常的な節約
ここでは、生活費を守るための具体的な方法について詳しく説明します。
それぞれの方法を組み合わせることで、安心して支援を利用できる環境を整えましょう。
自立支援医療制度の活用
自立支援医療制度を活用することで、医療費の自己負担を減らせます。
特に、定期的な通院や薬の処方が必要な場合、大きな助けとなる制度です。
- 医療費の自己負担が原則1割
- 所得に応じた負担上限額
- 精神疾患、身体疾患などが対象
- 申請は自治体の窓口で
たとえば、月1万円の通院費用がある場合、この制度を利用すると月1,000円に軽減されます。
申請手続きには、主治医の診断書や申請書類が必要です。
医療費の負担を減らすことで、他の生活費に回せる余裕が生まれます。
利用を検討する際は、自治体窓口で詳しい説明を受けましょう。
障害者手帳の取得
障害者手帳を取得することで、税金の減免や公共交通機関の割引など、生活費を削減できる特典を受けられます。
手帳の取得は生活費を守るうえで効果的な方法です。
- 税金や公共料金の減免
- 公共交通機関の割引
- 携帯料金の割引プラン
- 公的施設の利用料の無料化
たとえば、電車やバスの運賃が半額になる地域も多く、毎日の通勤や通所にかかる交通費を大幅に節約できます。
手帳の申請には、診断書や写真などの必要書類を用意し、市区町村の窓口で手続きを行います。
障害者手帳を活用することで、日々の生活費を効果的に削減できるようになります。
日常的な節約
日常生活の中で節約を心がけることで、生活費を守ることができます。
小さな工夫を積み重ねることで、毎月の支出を抑えることが可能です。
- 格安スマホへの変更
- 外食を控え自炊を増やす
- サブスクリプションの見直し
- 中古品やリサイクル品の活用
たとえば、格安スマホに変更することで、毎月の通信費を大幅に削減できます。
さらに、外食を減らして自炊を増やすことで、食費を抑えつつ健康的な食事を楽しむことが可能です。
支出を抑えるためには、まず現在の生活費の内訳を見直し、削減できる部分を探しましょう。
こうした節約を習慣化することで、就労移行支援中の生活を安定させられます。



生活費を守るためには、制度の活用や節約が重要です。
無理のない範囲で取り組んでみましょう。
Q&A


- 移行就労支援を利用する際にかかる費用はどれくらいですか?
-
移行就労支援の利用料金は、世帯の所得状況に応じて負担上限額が設定されています。
- 生活保護世帯・住民税非課税世帯:0円
- 住民税課税世帯(所得16万円未満):9,300円
- それ以上の所得の場合:37,200円
たとえば、住民税非課税世帯であれば利用料金は無料です。一方、所得が高い場合は月額37,200円の負担が必要です。負担上限額は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
- 移行就労支援の利用料金以外に発生する費用は何がありますか?
-
利用料金以外にも、以下のような費用が発生する場合があります。
- 交通費:自宅から事業所や企業見学への移動費
- 食事代:昼食、飲み物、間食などの費用
例えば、公共交通機関を利用して事業所まで通う場合、往復分の交通費が必要です。また、昼食代や飲み物代も発生します。事業所によっては、交通費の補助制度を利用できる場合もありますので、確認してみましょう。
- 移行就労支援利用中の主な収入源にはどのようなものがありますか?
-
移行就労支援利用中の主な収入源は以下の通りです。
- 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
- 雇用保険の基本手当(給付金)
- 傷病手当金
- 生活保護
- 家族からの援助
例えば、障害基礎年金の場合、1級で年間約97万円、2級で年間約78万円を受給できます。また、生活保護では生活費や医療費、家賃補助などが支給されます。それぞれの制度の利用条件や申請手続きについては、自治体窓口や専門の相談機関で確認してください。
- 就労移行支援を利用しながらアルバイトは可能ですか?
-
基本的に、就労移行支援を利用しながらアルバイトをすることは制限されています。ただし、自治体によって判断が異なる場合もあるため、事業所や自治体に確認することをおすすめします。
- 原則アルバイトは禁止
- 支援プログラムに専念する必要あり
- 例外として、自治体が許可する場合もあり
アルバイトを希望する場合は、事前に事業所や自治体へ相談し、適切な手続きや許可を得ることが大切です。
- 移行就労支援中の生活費を守るためにはどうすればよいですか?
-
生活費を守るためには、以下の方法を組み合わせることが重要です。
- 自立支援医療制度の活用(医療費の自己負担が軽減)
- 障害者手帳の取得(公共交通機関の割引、税金の減免などの特典)
- 日常的な節約(格安スマホの利用、自炊の増加、サブスクリプションの見直し)
例えば、障害者手帳を取得することで公共交通機関の運賃が半額になったり、自立支援医療制度を利用することで医療費負担が1割に軽減されたりします。日常的な支出を見直し、制度を活用することで、生活費を効果的に管理できます。
まとめ


- 利用料金は世帯収入に応じて負担上限が設定されており、低所得世帯では負担が軽減される
- 利用料金以外にも交通費や食事代などの費用が発生する場合がある
- 障害年金や生活保護などの収入源を活用することが重要
- 生活費の負担を軽減するために支援制度や日常的な節約を組み合わせる
移行就労支援を利用する際の費用は、利用料金と交通費や食事代などの個人的な出費を含みます。利用料金は世帯の所得状況に応じて変動し、生活保護世帯や住民税非課税世帯は0円、住民税課税世帯(所得16万円未満)は9,300円、それ以上は37,200円が上限です。
利用中は、障害年金や生活保護といった公的な収入源を活用し、医療費を軽減する自立支援医療制度や交通費を補助する制度を利用することで、生活費の負担を減らすことが可能です。
また、日常的な節約や障害者手帳の特典を活用することで、経済的な安定を図りながら就労移行支援に集中できる環境を整えられます。



生活費に不安がある場合は、自治体の窓口や専門の相談機関で相談してみましょう。
利用できる制度を活用しながら、安心して支援を受けましょう。