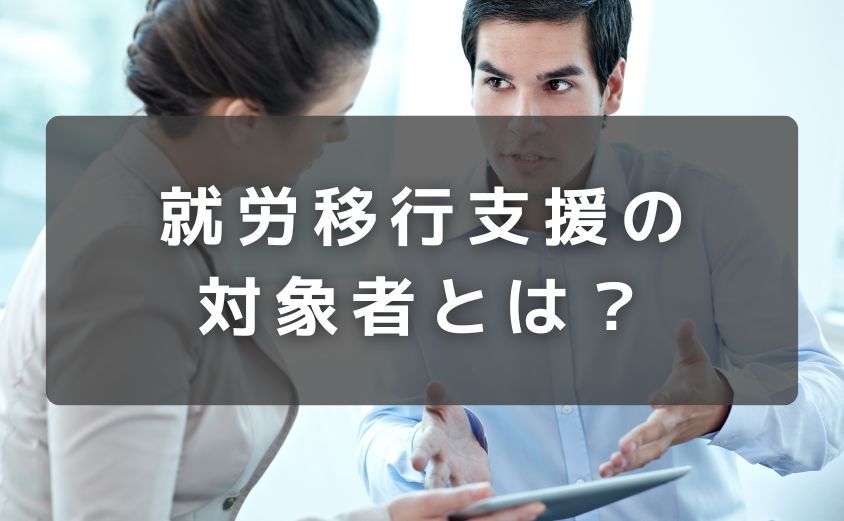「就労移行支援の対象者って、どんな人なんだろう?」
そんな疑問を抱えていませんか?ネットや周りの情報を調べても、「障害を持つ人が利用できるサービス」といった曖昧な説明が多く、自分が対象者に当てはまるのか分からず悩む方も少なくありません。もしかすると、「条件に当てはまらないかも」「利用したいけど、問い合わせる勇気が出ない」と感じているかもしれませんね。
この記事では、「就労移行支援の対象者」に関する疑問に寄り添いながら、具体的な条件や利用できる可能性についてわかりやすく解説します。また、「対象者に該当するかどうか不安」という気持ちを抱えていた方が、実際に利用して就職を成功させた事例もご紹介。この記事を読むことで、就労移行支援を利用するための第一歩を自信を持って踏み出せるはずです。
例えば、精神疾患を抱えながらも「自分は対象者ではない」と思い込んでいたCさん。記事で条件や利用方法を知り、勇気を出して事業所に相談したことで支援を受けることができました。半年後には、希望する職種に就職を果たし、今では充実した社会生活を送っています。
この記事を読むことで得られる具体的なメリットは次の通りです:
- 就労移行支援の対象者となるための条件が詳しく理解できる
- 自分が対象者かどうか判断するポイントがわかる
- 就労移行支援を利用することで得られる具体的な支援内容が見えてくる
就労移行支援は、うつ病や発達障害、その他の疾患を持つ方々をはじめ、多岐にわたる状況に対応しています。「自分なんかは利用できない」と諦める前に、まずは対象者に関する正確な情報を知り、可能性を確認してみませんか?
就労移行支援事業所とは
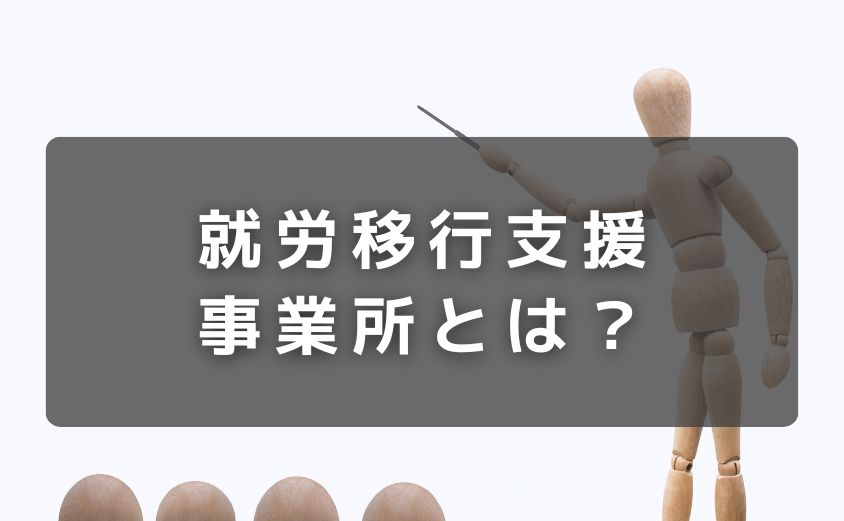
就労移行支援事業所は、障がいや難病を持つ方が一般企業への就職を目指すための支援サービスです。
利用者が職業スキルを身につけ、安定して働けるようになることを目指しています。

就労移行支援事業所を利用することで、自信を持って就職に挑める準備が整いますよ。
- 就労移行支援の概要
- 就労移行支援の利用期間
- 就労移行支援の利用料金
- 就労移行支援と就労継続支援の違い
以下では、就労移行支援の具体的な概要や特徴について詳しく解説していきます。
就労移行支援の概要
就労移行支援とは、障がいや難病を持つ方が、一般企業への就職を目指すための福祉サービスです。
利用者が必要なスキルや知識を習得し、自立した社会生活を送れるようサポートします。
- 職業訓練の提供
- 就職活動のサポート
- 職場定着のためのフォローアップ
たとえば、就労移行支援事業所では、ビジネスマナーやパソコンスキル、コミュニケーションスキルなどの訓練が行われます。
また、就職活動時には、求人情報の提供や履歴書作成のアドバイス、面接練習など、就職成功に向けたサポートも受けられます。
さらに、就職後も職場定着に向けた支援が継続して行われるため、安心して働き続けることが可能です。
就労移行支援を利用することで、自分に合ったペースでスキルを習得し、無理なく就職を目指せます。
就労移行支援の利用期間
就労移行支援の利用期間は、原則として最大で2年間とされています。
ただし、利用者の状況や進捗に応じて、延長が認められる場合もあります。
- 利用期間の目安は2年
- 状況に応じて延長が可能
たとえば、一般企業への就職が難しい場合や訓練が十分でない場合には、個別の事情を考慮して延長が認められることがあります。
就労移行支援を計画的に活用し、最終的には自立した社会生活を目指しましょう。
就労移行支援の利用料金
就労移行支援の利用料金は、原則として利用者の収入や世帯の所得に応じて決まります。
多くの場合、自己負担額は無料または低額で利用できる仕組みとなっています。
- 所得区分により無料の対象もあり
- 月額の上限負担額が設定されている
- 世帯所得に応じた3段階の負担額
たとえば、低所得世帯(住民税非課税世帯)や生活保護世帯では、自己負担額が無料となるケースが多いです。
また、中所得世帯や高所得世帯の場合でも、福祉サービスの一環として、月額の負担上限額が3,000円~37,200円に設定されています。
このように、負担額が収入や所得に応じて調整されるため、多くの方が経済的な負担を感じることなく利用できます。
就労移行支援と就労継続支援の違い
就労移行支援と就労継続支援は、どちらも障がいのある方を支援する福祉サービスですが、目的や対象者が異なります。
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方を支援するのに対し、就労継続支援は、継続的に福祉的就労を行う方を支援するものです。
- 就労移行支援:一般企業への就職を支援
- 就労継続支援:福祉的就労の場を提供
- 対象者の就労希望や能力で選択
たとえば、就労移行支援は、スキルを習得して一般企業に就職したい方が対象です。
一方、就労継続支援では、体力や健康上の理由から一般就労が難しい方に、継続的な就労の場が提供されます。
利用者の状況や希望に応じて、どちらの支援を利用するかを選ぶことが重要です。
次に、移行就労支援の対象者について詳しく見ていきます。
就労移行支援の対象者
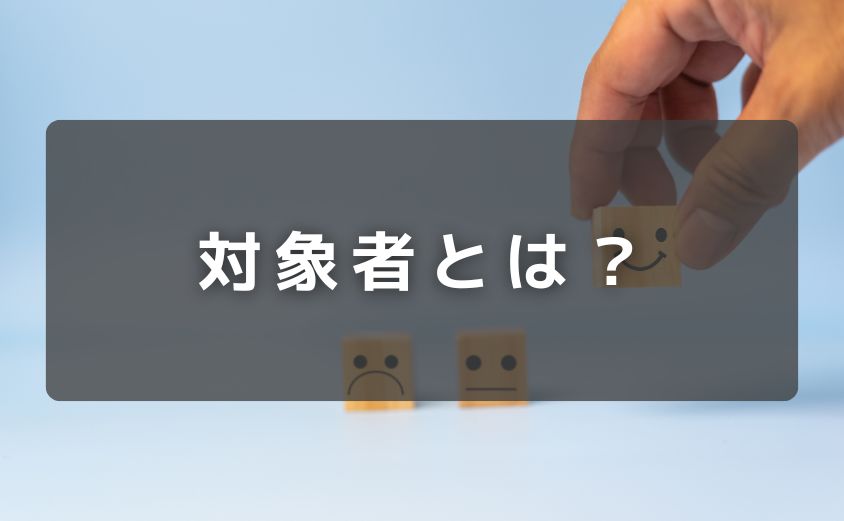
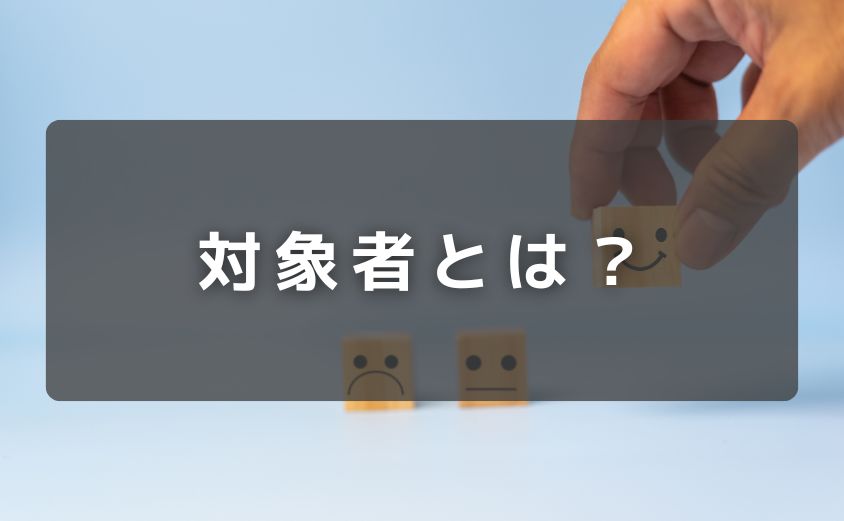
就労移行支援は、障がいや難病を持ちながらも一般企業での就労を希望する方を対象にしています。
対象者は、年齢や障がいの種類、就労意欲の有無などの条件を満たす必要があります。



就労移行支援は「働きたい!」という意欲をサポートするサービスです。
- 障がいや難病を持つ方
- 一般企業に就職を希望する方
- 18歳以上65歳未満の方
以下で、対象者の詳細についてさらに具体的に説明していきます。
障がいや難病のある方
就労移行支援は、主に障がいや難病を持つ方を対象としています。
具体的には、知的障害、身体障害、精神障害、または難病のある方が利用できます。
- 知的障害:学習や理解に困難がある方
- 身体障害:身体的な制約がある方
- 精神障害:メンタル面での支援が必要な方
- 難病:長期的な療養が必要な方
たとえば、知的障害のある方には、スキルを段階的に学べるように個別支援計画を立てます。
身体障害のある方には、職場環境の調整や適切な訓練を提供することで、働きやすい状況を整えます。
精神障害の方には、就労に向けたメンタルケアやストレス管理を重視した支援が行われます。
このように、障がいの種類や状況に合わせた柔軟な支援が特徴です。
一般企業に就職したい方
就労移行支援は、一般企業への就職を目指している方に特化したサービスです。
「普通に働きたい」「安定した収入を得たい」という希望を持つ方が対象となります。
- 一般就労を目指す意欲がある方
- 安定した収入を得たいと考える方
- 長期的に働き続ける目標を持つ方
たとえば、以前働いていたが職場での環境が合わずに退職した方も、就労移行支援を通じて適切な仕事を見つけることができます。
また、未経験の職種に挑戦したい方には、訓練を通じて必要なスキルを習得するサポートが行われます。
これにより、就職の可能性が広がり、自信を持って職場に適応できるようになります。
年齢条件
就労移行支援は、原則として18歳以上65歳未満の方が対象となります。
ただし、例外的に65歳以上でも利用できる場合があります。
- 原則18歳以上の方が対象
- 65歳未満が基本の対象範囲
- 65歳以上でも例外的に利用可能
たとえば、65歳以上の方でも、就労意欲があり、医師の診断や意見書で適切と判断される場合には利用が認められることがあります。
また、定年後に新たなキャリアを築きたいと考えている方も、条件を満たせば利用可能です。
このように、年齢の制限があっても柔軟な対応が取られています。
次は、就労移行支援の利用条件について解説します。
就労移行支援の利用条件
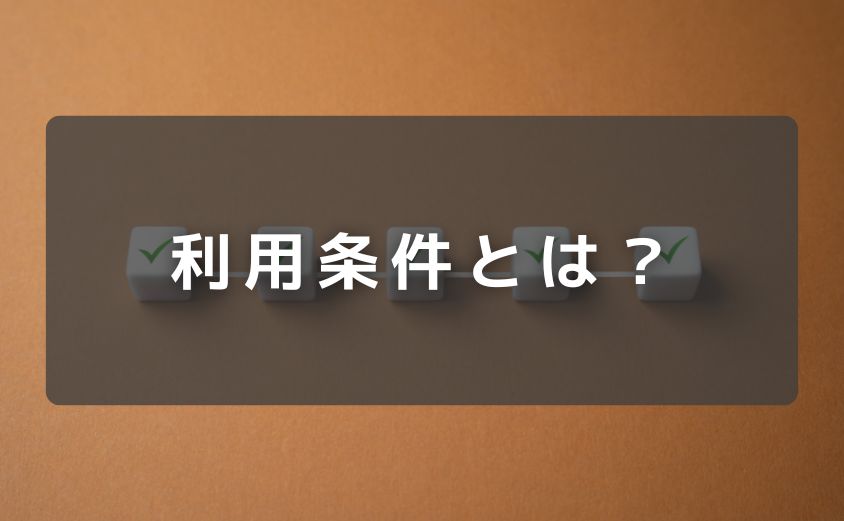
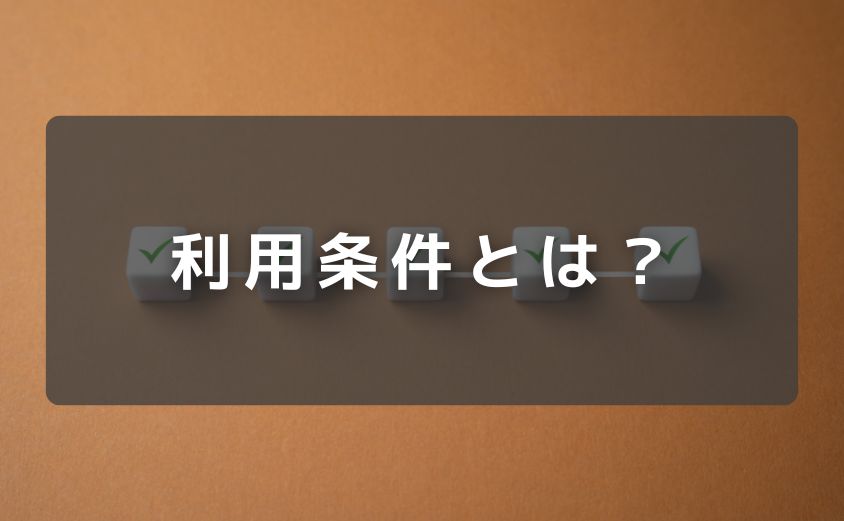
就労移行支援を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
主に障がいの程度や種類、就労意欲、医師の診断書などが重要なポイントです。



支援を受ける条件を確認し、自分が対象かどうかチェックしましょう。
- 障がいの程度と種類
- 就労意欲と可能性
- 医師の診断と意見書
以下で、具体的な条件について詳しく解説します。
障がいの程度と種類
就労移行支援は、障がい者手帳を持つ方、または医師の診断により障がいが認められる方が対象です。
障がいの程度や種類に応じて、支援の内容が調整されます。
- 身体障害:動作や移動の制限がある方
- 精神障害:メンタルヘルスケアが必要な方
- 知的障害:学習や判断に困難がある方
- 難病:長期的な治療を必要とする方
たとえば、精神障害を持つ方にはストレス管理を重視したプログラムを提供します。
また、身体障害のある方には、職場環境の調整や身体的負担を軽減するための支援が行われます。
障がいの程度や状況に応じて、適切なサポートが受けられる仕組みです。
就労意欲と可能性
就労移行支援を利用するには、就労意欲があり、可能性があることが重要です。
「働きたい」「自立したい」という思いがある方が対象となります。
- 就職を希望している方
- 働く意欲がある方
- 自立した生活を目指している方
たとえば、就職活動に前向きな方には、具体的な目標設定や面接対策の支援が提供されます。
働きたいという思いが強い方には、スキル習得のためのプログラムが重点的に行われます。
このように、利用者の意欲を尊重し、働く力を引き出すことが支援の基本方針です。
医師の診断と意見書の必要性
就労移行支援を利用するには、医師の診断書や意見書が必要となる場合があります。
これは、障がいの程度や就労可能性を正確に把握するためです。
- 診断書や意見書で適性を確認
- 医師の意見を基に支援計画を策定
- 診断が支援利用の判断基準に
たとえば、精神的な障がいがある方の場合、医師の意見を基にメンタルケアを重視した支援計画が立てられます。
また、身体障害の方には、診断書を基に職場環境の調整や適応訓練が提供されます。
これにより、利用者に合った支援が行われ、スムーズな就職が可能になります。
次に、就労移行支援のサービス内容について解説します。
就労移行支援のサービス内容


就労移行支援では、利用者がスムーズに就職し、安定した職場環境を維持できるよう、さまざまなサービスが提供されます。
主に職業訓練、就職活動のサポート、職場定着支援が含まれます。



サービスを活用することで、自信を持って就職を目指すことができますよ!
- 職業訓練
- 就職活動のサポート
- 職場定着のためのサポート
以下で、各サービス内容について詳しく解説します。
職業訓練
職業訓練では、就職に必要なスキルを習得するためのサポートが行われます。
具体的には、ビジネスマナーやコミュニケーションスキル、職業スキルの習得が含まれます。
- ビジネスマナーの習得
- コミュニケーションスキルの向上
- 職業スキルの習得
たとえば、ビジネスマナーの習得では、挨拶の仕方や身だしなみ、電話対応など、職場で必要な基本スキルが学べます。
コミュニケーションスキルの訓練では、他人と円滑にやり取りできる力を養うための練習やロールプレイが行われます。
また、職業スキルの習得では、パソコンの基本操作や特定の職種で求められる技能が指導されます。
このように、利用者が自信を持って職場に適応できるよう、丁寧な指導が行われます。
就職活動のサポート
就労移行支援では、就職活動をスムーズに進めるための支援が提供されます。
具体的には、求人情報の提供、履歴書・職務経歴書作成の支援、面接対策などがあります。
- 求人情報の提供
- 履歴書・職務経歴書の作成支援
- 面接対策
たとえば、求人情報の提供では、利用者の希望や適性に合った求人を探し、紹介するサポートが行われます。
履歴書や職務経歴書の作成支援では、アピールポイントの書き方や適切な言葉の選び方をアドバイスします。
さらに、面接対策では、模擬面接を通じて自信をつける練習ができます。
これにより、就職活動を円滑に進められる体制が整います。
職場定着のためのサポート
就労移行支援では、就職後の職場定着を目的としたサポートも行われます。
職場でのトラブルやストレスを軽減し、長く働き続けられるよう支援することが目的です。
- 就職後のフォローアップ
- 職場との連絡調整
- 定着支援計画の策定
たとえば、就職後に職場での悩みや不安があれば、支援スタッフが相談に乗り、適切な対応を取ります。
また、職場との連絡調整を通じて、利用者が働きやすい環境を作るための交渉やサポートを行います。
定着支援計画では、利用者の特性や職場の状況に応じて長期的な支援プランを策定します。
これにより、安心して働き続けられる職場環境が整います。
次は、就労移行支援を利用する際の注意点について解説します。
就労移行支援を利用する際の注意点
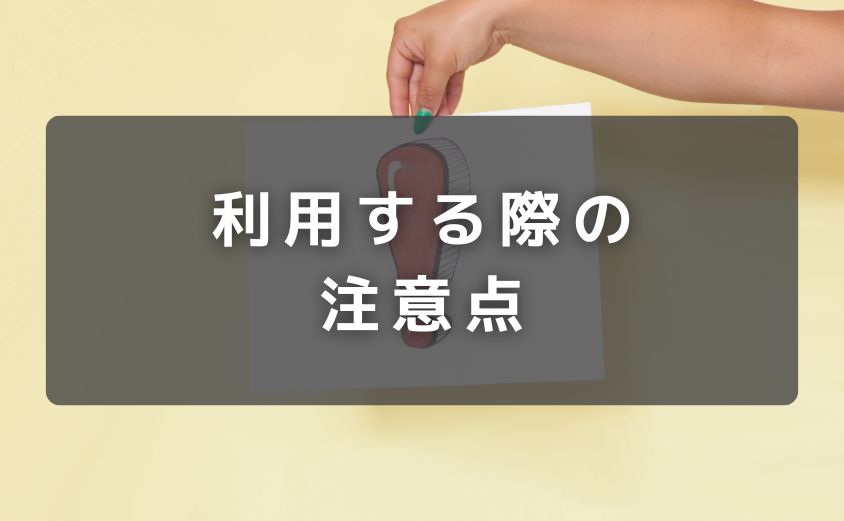
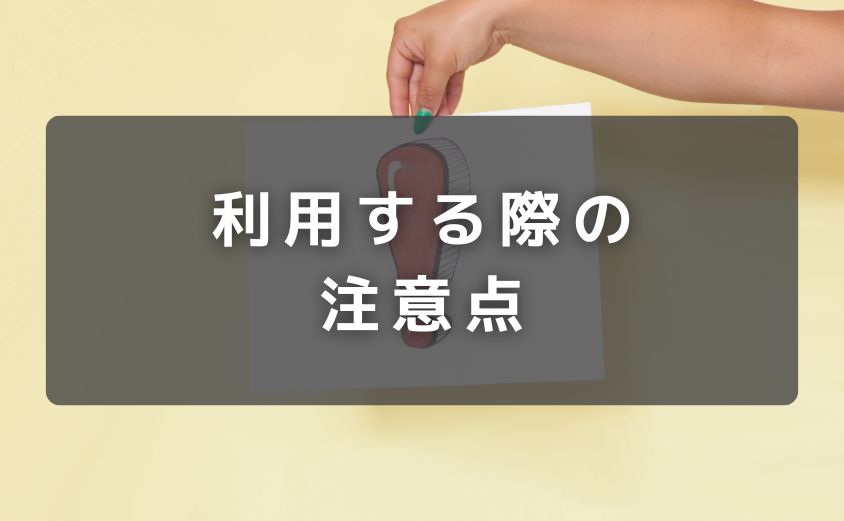
就労移行支援を利用する際には、自分に合った事業所を選ぶことや、必要な手続きを正しく行うことが重要です。
また、生活費や収入についても事前に考慮しておくことが大切です。



準備をしっかり整えて、スムーズに支援を利用しましょう!
- 自分に合った事業所の選択
- 障害福祉サービス受給者証の取得方法
- 利用期間中の生活費と収入
以下で、注意点を詳しく解説していきます。
自分に合った事業所の選択
就労移行支援を利用する際には、事業所の特色や支援内容を確認し、自分に合った事業所を選ぶことが大切です。
見学や体験を通じて、事業所の雰囲気やスタッフの対応などをチェックしましょう。
- 事業所の特色と支援内容を確認
- 見学や体験で雰囲気を確認
- スタッフの対応をチェック
たとえば、ある事業所ではパソコンスキルに特化した訓練を提供している場合もあれば、別の事業所では軽作業を中心とした訓練が行われています。
また、スタッフとの相性も重要です。困ったときに親身になって相談に乗ってくれるかどうかも選択のポイントです。
このように、事業所を選ぶ際は、自分の目で確認し、納得のいく選択をすることが大切です。
障害福祉サービス受給者証の取得方法
就労移行支援を利用するためには、障害福祉サービス受給者証を取得する必要があります。
受給者証を取得するには、自治体の福祉窓口で申請手続きを行います。
- 自治体の福祉窓口で申請
- 必要書類を準備する
- 手続き後、受給者証が発行される
たとえば、申請時には、障害者手帳や医師の意見書、申請書類などが必要です。
受給者証の発行には時間がかかる場合があるため、早めの準備が必要です。
手続きについて分からない場合は、福祉窓口や移行支援事業所のスタッフに相談するとスムーズです。
利用期間中の生活費と収入
就労移行支援を利用する期間中の生活費や収入についても、事前に考慮しておくことが大切です。
利用期間中はアルバイトが可能な場合もあり、一定の収入を得ることができます。
- アルバイトが可能な場合がある
- 生活費の確保を計画的に行う
- 自治体の生活支援制度を活用
たとえば、アルバイトをしながら移行就労支援を利用することで、生活費を補いながらスキルを習得できます。
また、自治体が提供する生活支援制度や福祉サービスを活用することで、経済的な負担を軽減することも可能です。
これにより、安心して支援を受ける環境を整えられます。
Q&A


- 就労移行支援とは何ですか?
-
就労移行支援は、障がいや難病を持つ方が一般企業への就職を目指すための福祉サービスです。利用者が必要なスキルや知識を習得し、自立した社会生活を送れるようサポートします。
- 就労移行支援の利用期間はどのくらいですか?
-
利用期間は原則として最大2年間とされています。ただし、利用者の状況や進捗に応じて、延長が認められる場合もあります。
- 就労移行支援の利用料金はどれくらいかかりますか?
-
利用料金は利用者の収入や世帯所得に応じて決まります。多くの場合、自己負担額は無料または低額で、住民税非課税世帯や生活保護世帯では無料となるケースが一般的です。
- 就労移行支援と就労継続支援の違いは何ですか?
-
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方を対象としています。一方、就労継続支援は、一般就労が難しい方に福祉的就労の場を提供するサービスです。
- 就労移行支援ではどのようなサービスが提供されますか?
-
職業訓練(ビジネスマナー、パソコンスキル、コミュニケーションスキルの向上など)、就職活動のサポート(求人情報提供、履歴書作成支援、面接練習など)、さらに就職後の職場定着を目的としたフォローアップ支援が提供されます。
- 就労移行支援を利用するにはどのような条件がありますか?
-
対象は18歳以上65歳未満の障がいや難病を持つ方で、一般企業への就職を希望する方です。医師の診断書や障害者手帳が必要となる場合があります。
- 就労移行支援を利用する際の注意点は何ですか?
-
自分に合った事業所を選ぶことが重要です。事業所の見学や体験を通じて、支援内容や雰囲気を確認してください。また、障害福祉サービス受給者証の取得手続きを早めに行うことや、利用期間中の生活費や収入計画も考慮しましょう。
まとめ


- 就労移行支援は障がいや難病を持つ方が一般企業への就職を目指すための支援サービス。
- 職業訓練、就職活動のサポート、職場定着のフォローアップが主なサービス内容。
- 利用期間は原則2年だが、状況に応じて延長可能。
- 利用料金は収入や世帯所得に応じて無料または低額。
- 利用するには障害者手帳や医師の診断書が必要な場合がある。
就労移行支援は、自立した社会生活を目指す方の強い味方です。職業スキルの習得から就職後の定着支援まで、幅広いサポートが受けられるので、自信を持って新しい一歩を踏み出すことができます。
利用を検討される方は、自分に合った事業所を選び、必要な手続きを整えることが大切です。準備をしっかり行い、支援を最大限に活用しましょう!



まずは近くの就労移行支援事業所に相談してみましょう。親身にサポートしてくれるスタッフがきっと見つかります!
無料での見学や体験もできる場合が多いので、気軽に問い合わせてみてくださいね。